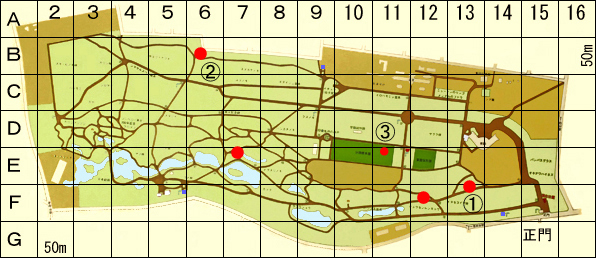| 名前の由来 イヌビワ Ficus erecta |
イヌビワ : 「劣ったビワ」の意味。 |
正確には、「ビワに似ているが、ビワより劣っている」という意味になる。
イヌを冠する植物はたくさんあるが、「イヌ」はもちろん動物の犬ではなくて、「元の植物・本家に比べて劣っている」あるいは「役に立たない」という意味で使われている。
それはともかくとして、何がビワに似ているのか?
まずは両者の葉を較べてみよう。 |
|
| イヌビワの葉 |
ビワの葉 |

イヌビワの葉は先の尖った「楕円形」で、普通の葉の形である。鋸歯もなく無毛ですべすべしている。
ビワの葉は「狭い楕円形」。一面に毛が生えており、粗い鋸歯があって表面は凸凹している。 |
 |
ご覧のように全然似ていない。
やはり似ているのは「実」とすべきであろう。
実の形がビワに似ているが、食べるほどのものではない、ということである。 実際に食べてみたことがあるが、まだ熟していなかったためか、まずくて食べられなかった。
個人的には、イヌビワ の別称の一つ「コイチジク」が適切であると思う。
|
|
| 種小名 erecta : 「直立する」という意味。 |
イヌビワの実(花の集まりで、果嚢という)は葉の腋に付く。
垂れ下がることもあるが、普通は長い果柄で上向きに付く。
これが erecta の由来であろう。
|
 |
|
Ficus イチジク属 無花果属 : |
Ficusはイチジクのラテン語の古名に由来しているというが、その古名や意味は不明である。
世界の熱帯から暖帯まで約 800種ある。
|
| イチジク Ficus carica Linn. |
|
「イチジク」の和名の由来は、ペルシア語 anjir を音訳した漢名「映日果」(インジェクオ) がイチジクに転訛したものである。 『花と樹の大事典』
漢字の「無花果」は中国名で、それを「イチジク」に当てている。
無花果は、イチジクの花が外からは見えない「花嚢」の中にあり、そのまま果実となるところから名付けられた。 |
|
| イチジクの実 |
イチジクの葉 |
 |

|
左の写真の実はまだ青い。
実の付き方はイヌビワと同じだが、果柄はほとんどない。
|
|
| クワ科 Moraceae : mor (黒の意) から。 |
クワに対するラテン古名に由来する。そのもともとの語源はケルト語の mor で、熟した時の黒いクワの実にからきている。
|
|
|
アカグワ |
日本には6種ものクワが自生しているが、種類を特定できている写真がないため、外国産の写真を載せる。
|
 |
Morus rubra Linn. (1753)
アーノルド植物園 |
|
|