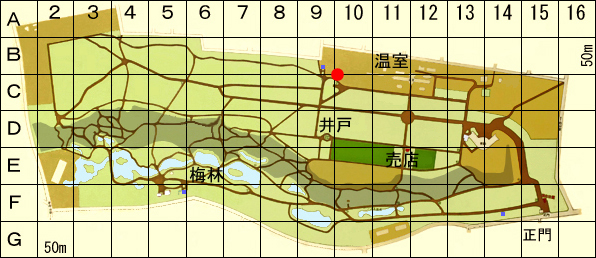| form. rosea : チャの 淡紅色種 |
初め牧野は「変種」としたが、後に 下のランクの「品種」とされた。現在の遺伝子解析による分類では、恐らく チャと「同種」だろう。
昔の分類学は 主に形態の違いをもとにしており、花の色の違いでも サブのレベルで学名を付けていた。 |
|
チャ 茶 : 苦い木 の意味から |
読みは中国名、茶 cha の音から。
茶の字は元 「荼」で、にがい意味の「苦」からきた。 読みは「余」の字の音が転じた「ト、ダ」である。 後に「茶」と書くようになり、「荼」はニガナの意味で用いるようになった。 『角川漢和中辞典』
天平時代(8世紀前半)に伝わったという説がある。 中国の茶文化を伝え広めたのは、1191年に帰国した栄西を初めとした臨済宗の僧によるということである。 |
|
種小名 sinensis : 中国産の |
|
|
Camellia 属 : 人名による |
17世紀後半 チェコに生まれ、フィリピンで宣教活動と動植物の研究を行った Georg J. Kamel (1661-1706)を顕彰したものであるが、リンネは頭文字の K を C としている。ラテン語では K を使うことがほとんどないためだろう。
和名はツバキ属、中国では 山茶属 あるいは茶属である。 |
|
ツバキ科 Theaceae : |
ツバキ科の基準属は Camellia属であるが、科名は ツバキ属の チャ 茶 cha、tcha から生じた thea が使われ、科名は「保留名」となっている。
保留名となった経緯については チャ の項を参照。 |
|