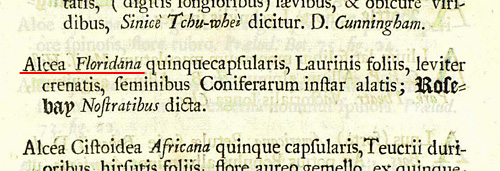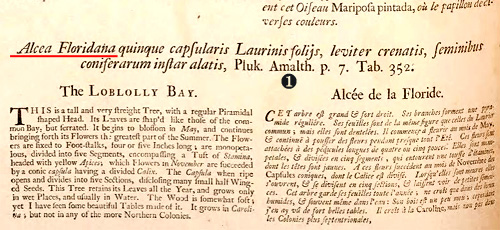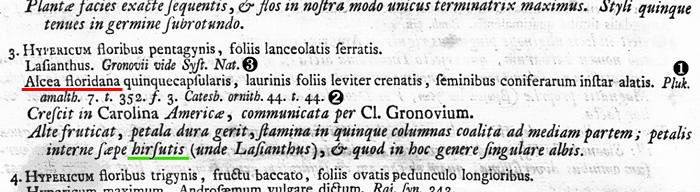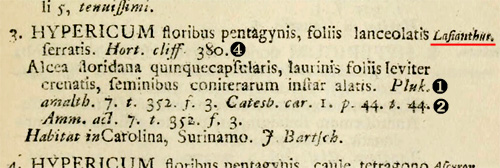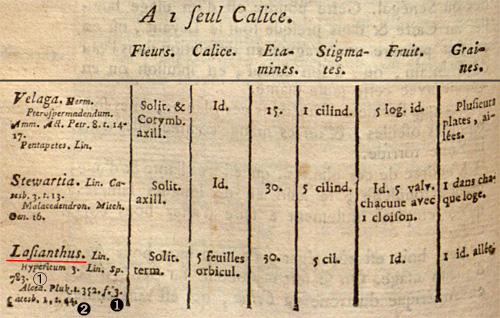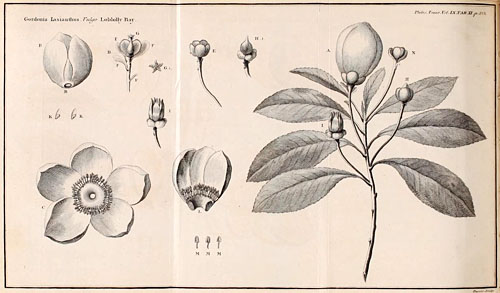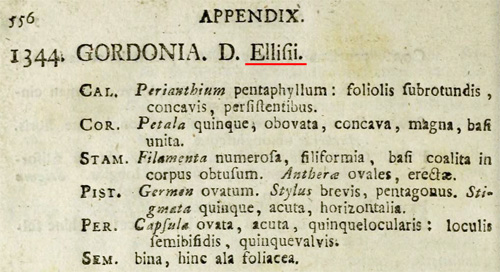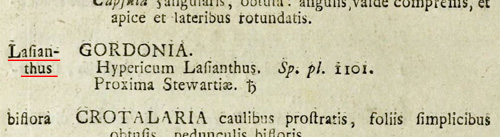|
|
前掲の、❶プルークネット と ➋ケイツビーの参考文献を挙げている。
6~7行目の説明文に「花弁の内側が、しばしば hirsutis 髭毛がある(そのため Lasianthus とされる),」とある。 |
| リンネはこの記載を踏まえて『植物の種』での名称を Hypericum lasianthus としたことがわかった。しかし、なぜオトギリソウ属としたのだろうか? |
|
| |
| |
| | | 『植物の種』以降の出版、記載た | 基準日:1753年5月1日 | |
| | |
| 年 | 学 名 | 命名者 | 属名・備考 など |
| ① |
1753 |
Hypericum lasianthus |
リンネ |
異名 |
|
|
| 『Species plantarum 植物の種』第2巻 p.783。 |
|
|
|
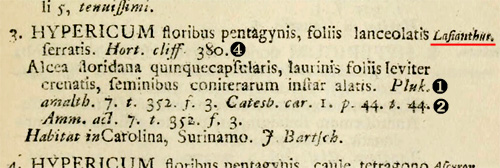 |
|
|
| 学名(属名)は異名だが、ここで種小名 lasianthus が有効となる。 |
| リンネがオトギリソウ属としたのは、カップ咲きの花・5体雄蕊・5裂する柱頭・5室の子房・花弁の周囲の突起など、花のみに注目したためである。雄しべ・雌しべの数や構成だけで人為的に分類する「性体系」の欠点が表れている。 |
| 本 種 |
キンシバイ |
 |
 |
| 本種の花弁の周囲に確かに毛のような突起がある▲。花弁の表面にもあるのかどうかは未確認。比較したのはキンシバイの品種 'ヒドコート'。 |
| 別の部位、例えば花のつき方をケイツビーの図で見れば、オトギリソウ属とは違うことがわかるはずで、恐らくリンネは 分かっていたはず。 |
|
|
|
|
| ② |
1763 |
Lasianthus属 |
アダンソン |
却下名 nom. rej. |
|
|
Michel Adanson (1727-1806) はフランスの博物学者。リンネの「性体系」分類を非難した人物のひとり。
Lasianthus属を記載した『Familles des plantes 植物の科』は様々な形質について植物を分析し、58の科を設定したもので、現在の分類の「目
もく」に近い。
Lasianthus属はアオイ科に分類されていて不正確だが、ナツツバキ属の近縁となっているのは正解。 |
アダンソン |
 |
|
|
|
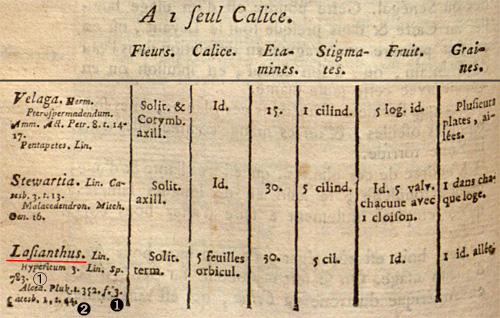 |
|
|
この表の項目は、左から 花・萼・雄しべ・柱頭・果実・種子。
種小名の記載が無いが、参考文献から 現 Gordonia属であることがわかる。もしも ① Hypericum lasianthus を引き継ぐと、属名と種小名が同じ L. lasianthus となり、現在の植物の規約では認められていない「反復名 tautonym」となってしまう。
そのことが影響したのかどうかは不明だが、ツバキ科 Lasianthus属は「却下名 nom. rej.」 となった。 |
|
|
|
|
| ③ |
1771 |
Gordonia属 |
エリス |
保留名 nom. cons. |
|
|
Gordonia lasianthus |
|
正名 |
|
|
| John Ellis (1710頃-1776) は、イギリスの布地のリネンを販売する商人で、博物学者。王立協会の会員に選ばれて、西フロリダやドミニカの王室調査官に任命された。北アメリカから植物や種子を移入し、リンネを含む多くの植物学者と文通を行っていた。 |
| 本種が記載されたのは協会のジャーナル『Philosophical transactions of the Royal Society of London』第60巻
(1770年版、出版は1771年) p.518~で、1770年12月にリンネに宛てた手紙を掲載したもの。属名を顕彰した ゴードン氏について、エリスは「卓越した園芸家」で二人(エリスとリンネ)の共通の「価値ある友人」と書いている。 |
|
|
|
その前文には「(本種は)ミラー氏の言う Hibiscus でも、リンネ博士が提唱する Hypericum でもなく、エリス氏の新しい Gordonia属になるもの」と紹介されている。
観察個体はロンドン・クラッパムで咲いたもので、アメリカから移入されたもの。
Dear Sir、以下の手紙の部分は省略。 |
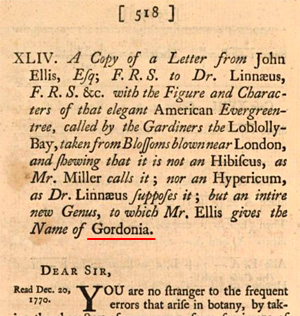 |
|
|
|
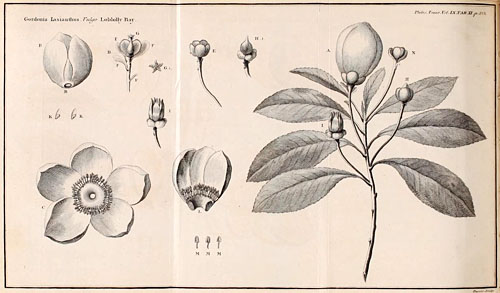 |
|
|
実物をしっかり見ているだけあって、詳細に描かれている。しかし、花弁周囲の微細な突起や長毛は表現されていない。はたして、花弁表面にも毛が生えているのだろうか?
② よりも後の記載だが、保留名となった。 |
|
|
|
|
| ④ |
1771 |
Gordonia属 |
リンネ | |
| |
| エリスからの手紙③で間違いを指摘されたリンネは、翌年に発行を予定していた『Mantissa plantarum Altera 植物補遺 後編』の最後の部分、
「Appendix 付録」 に、慌てて? Gordonia を付け加えた。 |
|
|
|
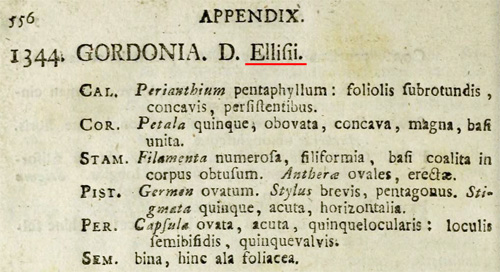 |
|
|
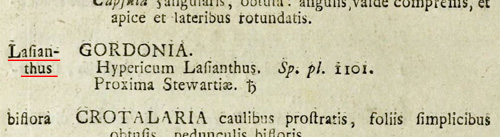 |
|
|
上:新属を追加し、命名者を Ellisii としていることから、③の後から刊行されたことがはっきりする。
下:種の記載。こちらには エリスの名前や文献が書かれていない。
自身の『植物の種』での記載ページを 783 とすべきところを、1101ページと間違えており、混乱を覗わせる。2行目に、③の手紙に書かれていた「ナツツバキ属に近縁」の注釈を入れている。 |
|
|
|
|
|
参考 その1: |
|
|
| 1823 |
Lasianthus属 |
ジャカン |
アカネ科 |
| |
たとえ別の科であっても、同名の属名は許されていないが、ツバキ科 Lasianthus属 が却下されたことによって、200年前にたてられた アカネ科 Lasianthus属が保留名として復活した。
適用されたのがいつなのかは不明。 |
|
| |
|
アカネ科 Lasianthus wallichii |
これぞ「長毛のある花」!
|
 |
flickr より
criative commons
by Bahamut Chao |
|
|
|
|
|
|
参考 その2: |
|
1826 |
Polyspora属 |
スウィート |
モッコク科として記載 |
|
|
Polyspora axillaris |
|
タイワンツバキ |
|
|
その後タイワンツバキは Gordonia属とされるが、現在は、ふたたび Polyspora属に戻されている。
詳しくは、別項 オオバタイワンツバキ 参照。 |
|
|
|
|
|
|
参考 その3: |
|
|
Gordonia属 |
Stackebrandt ほか |
バクテリアの属 |
|
|
| 植物・菌類(カビやキノコ)・藻類とは別物である「細菌」は、「国際原核生物命名規約」に従って命名されるため、同じ属名が存在しうる。 |
|
|
|