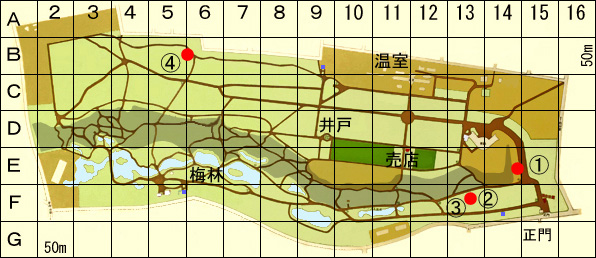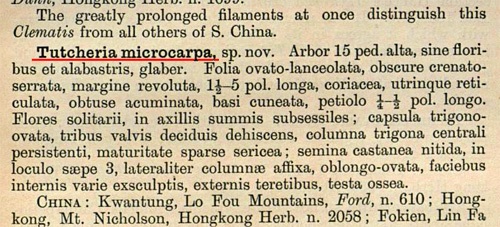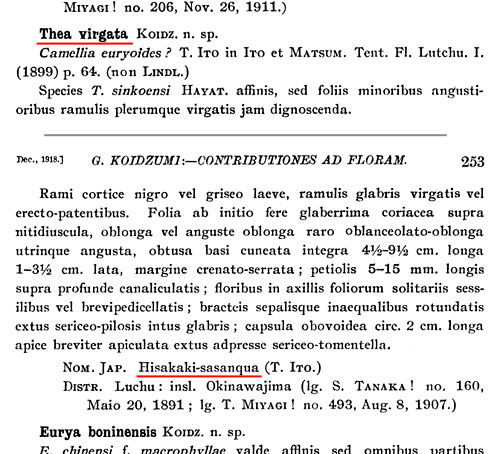| | | 『植物の種』以降の出版、記載た | 基準日:1753年5月1日 | |
| | |
| 年 | 学 名 | 命名者 | 属名・備考 など |
| ①P |
1826 |
Pyrenaria 属 |
ブルーム |
当時のモッコク科として記載 |
|
|
| Carl Ludwig von Blume (1796-1862) はドイツ生まれの植物学者。ジャカルタに派遣されて多くの植物標本を採取。ライデン大学教授、オランダ王立植物標本館館長を務め、多くの著作を残した。 |
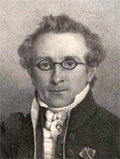 |
|
| Pyrenaria 属は『Bijdragen tot de flora van Nederlandsch Indië』p. 1120に記載。 |
|
|
|
| バラ科とされていたものを「萼 および 雄しべが合着している構造から、モッコク科とすべき」と、当時の Ternstroemiaceae に P. serrata を記載したが、その種は現在は有効ではないようだ。 |
|
|
|
| ②T |
1908 | Tutcheria 属 | ダン | モッコク科として記載 |
| | Stephen Troyte Dunn (1868-1938) はイギリスの植物学者で、中国、香港の植物に詳しい。そのほかの地域でも採取を行い、韓国や日本のコレクションもある。Tutcheria 属は『Journal of botany』第46巻 324ページに Ternstroemiaceae モッコク科の新属として記載した。
属名は同世代のイギリスの植物学者で、(仮称)香港植物森林局の副長官を17年間務めた William James Tutcher (1867-1920)を顕彰したもの。共著を出版したこともある。 |
|
|
|
|
| ② |
1909 |
Tutcheria microcarpa |
ダン |
本種の異名 basionym |
|
|
| 翌年のジャーナル 第47巻 197ページに、本種を新種として初めて記載した。この種小名が「先取権」を持っている。 |
|
|
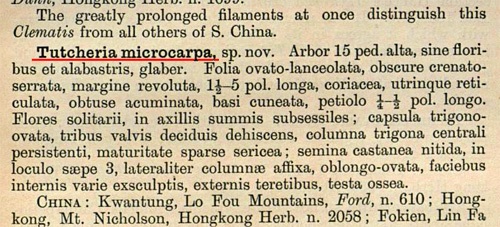 |
|
| 中国や香港の山中で採集したもの。ページ後半の掲載は割愛したが、ダンに本種の存在を教えてくれた 植物学者 Tutcher に属名を献上したことが書かれている。 |
| 日本では、この記載の存在が確認されていなかったようだ。 |
|
|
|
| |
| ③ |
1918 |
Thea virgata |
小泉 |
本種の異名 |
|
小泉源一 (1883-1953) は山形県出身の植物学者。日本植物分類標本園学会の創設者。京都大学教授。
本種の記載は『植物雑誌』第32巻、「Contributiones ad Floram Asiae Orientalis」の 252~253 ページで、新種としている。 |
|
|
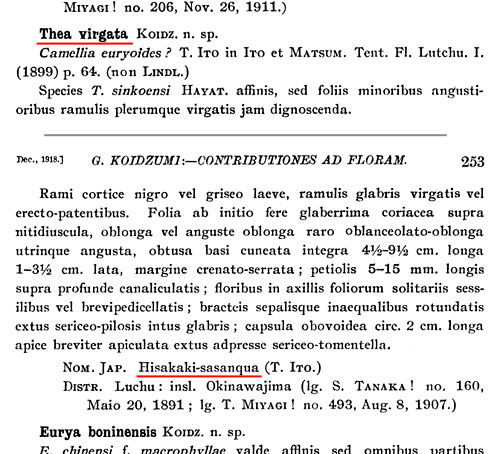 |
|
伊藤篤太郎が Camellia eutyoides か、としていた種を、新たにチャノキ属として種小名とともに記載した。
T. Ito (1866-1941)は愛知県出身の植物学者で、本草学者 伊藤圭介 は義理の祖父。 |
|
| 伊藤篤太郎による「ヒサカキサザンカ」の和名があったためか、②が知られていなかったためか、この学名が支持されたようだ。 |
|
|
|
|
1931 |
Camellia virgata |
牧野 & 根本 |
|
|
| 『日本植物総覧』第2巻 に記載したようだが、詳細は不明。 |
|
|
|
| ④ |
1940 |
Tutcheria virgata |
中井 |
本種の異名 |
|
『植物研究雑誌』第16巻 708ページに記載。③を訂正したもの。
その後 この学名が、長い間使われることになった。
同ページに、別種として②Tutcheria microcarpa Dunn (1909) が載っている。この時に、同種であることに気が付くべきだった。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ⑤ |
1972 | Pyrenaria microcarpa | ケン | GRINによる正名 |
|
|
②を訂正したもの。命名者の正式な発音は未確認。
Hsüan Keng (1923-2009)は現代の植物学者。国籍はわからないが、1972年当時にはシンガポール大学に所属。
『The Gardens' bulletin, Singapore』第26巻に、マレーシアで発見した2種の Pyrenaria属の新種を発表するとともに、Tutcheria 属が Pyrenaria 属の異名であることを指摘して、既存の9種を Pyrenaria 属に変更することを提案した。
すでに 50年前には訂正されていたのだ。 |
|
| ⑥ |
同 |
Pyrenaria virgata |
ケン |
本種の異名 |
| | | その9種の中には T. virgata を訂正したものも含まれており、異名のひとつとなっている。 | |
|
|