 |
|
|||
| 科 名 : | ナス科 Solanaceae | |||
| 別 名 : | タマサンゴ | |||
| 属 名 : | ナス属 Solanum Linn. (1735) | |||
| 英語名 : | Jerusalem cherry | |||
| 独語名 : | korallenstrauch | |||
| 原産地 : | メキシコから中南米に広く分布する。 | |||
| 用 途 : | 観賞樹として栽培される。 果実は有毒。 |
|||
 |
|
|||
| 科 名 : | ナス科 Solanaceae | |||
| 別 名 : | タマサンゴ | |||
| 属 名 : | ナス属 Solanum Linn. (1735) | |||
| 英語名 : | Jerusalem cherry | |||
| 独語名 : | korallenstrauch | |||
| 原産地 : | メキシコから中南米に広く分布する。 | |||
| 用 途 : | 観賞樹として栽培される。 果実は有毒。 |
|||
| 常緑の低木で春から秋にかけて花を咲かせ、夏から冬まで 橙色の実を付ける。 |
| 10年前 ①:ヒマラヤスギの足元 2001.9.8. |
 |
| ↓ |
| ①:少なくなった フユサンゴ 2013.1.27. |
 |
代わりに ほかの木の根元に広がっている。 |
 |
 |
| ②:ハリモミの足元 2012.8.9. |
 |
| フユの名が付いているが、撮影日からもわかるように「夏サンゴ」でもある。 |
| ②:葉の様子 2012.8.9. |
 |
| 葉は柔らかく 細長い。 |
| 花の様子 2002.5.19. |
 |
| フユサンゴ | ナス 2011.7.1. |
 |
 |
| ナス科の花は合弁花で、先が5つに裂けるものが多い。ナスとは同じ属なので、花の様子もよく似ている。 |
| 青い実 2001.9.8. |
 |
| 花後は順次実が大きくなっていくが、初めは緑色である。 |
| 赤い実 2001.12.8. |
 |
| ヒイラギ の 位 置 |
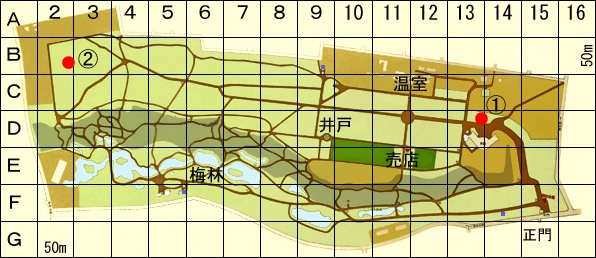 |
| 写真①: | D13 c | ● | 本館前、ヒマラヤスギの根元 |
| 写真②: | B2 d | ● | 針葉樹林、ハリモミの根元 |
| 名前の由来 フユサンゴ Solanum pseudocapsicum | |
和名 フユサンゴ 冬珊瑚 : |
|
|
| 英語名 Jerusalem cherry | |
|
| サクランボ 桜桃 | ミニトマト |
 |
 |
|
| 種小名 pseudocapsicum :トウガラシ(属)に似た の意味 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Solanum ナス 属 : | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ナスの花と実 | ||||||||||||||
 |
 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
ナス 科 Solanaceae : |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 植物の分類 : | APG II 分類による フユサンゴ の位置 |
| 原始的な植物 |
| ↑ | 緑藻 : | アオサ、アオミドロ、ミカヅキモ、など | |||||
| シダ植物 : | 維管束があり 胞子で増える植物 | ||||||
| 小葉植物 : | ヒカゲノカズラ、イワヒバ、ミズニラ、など | ||||||
| 大葉植物(シダ類): | マツバラン、トクサ、リュウビンタイ、ゼンマイ、オシダなど | ||||||
| 種子植物 : | 維管束があり 種子で増える植物 | ||||||
| 裸子植物 : | 種子が露出している | ||||||
| ソテツ 類 : | ソテツ、ザミア、など | ||||||
| イチョウ類 : | イチョウ | ||||||
| マツ 類 : | マツ、ナンヨウスギ、マキ、コウヤマキ、イチイ、ヒノキ、など | ||||||
| 被子植物 : | 種子が真皮に蔽われている | ||||||
| 被子植物基底群 : | アンボレラ、スイレン、など | ||||||
| モクレン亜綱 : | コショウ、モクレン、クスノキ、センリョウ、マツモ、など | ||||||
| 単子葉 類 : | ショウブ、サトイモ、ユリ、ヤシ、ツユクサ、ショウガ、など | ||||||
| 真生双子葉類 : | キンポウゲ、アワブキ、ヤマモガシ、ヤマグルマ、ツゲ、など | ||||||
| 中核真生双子葉類: | ビワモドキ、ナデシコ、ビャクダン、ユキノシタ、など | ||||||
| バラ目 群 : | |||||||
| バラ亜綱: | ブドウ、フウロソウ、フトモモ、など | ||||||
| マメ 群: | ハマビシ、ニシキギ、カタバミ、マメ、バラ、ウリ、ブナ、など | ||||||
| アオイ群: | アブラナ、アオイ、ムクロジ、など | ||||||
| キク目 群 : | |||||||
| キク亜綱: | ミズキ、ツツジ、など | ||||||
| 以前の分類場所 | ナス目 | ナス科、ヒルガオ科、ミツガシワ科、ハナシノブ科、など | |||||
| シソ 群 : | ガリア、リンドウ、ナス、シソ、など | ||||||
| ナス目 | ナス科、ヒルガオ科、など | ||||||
| ナス科 | トウガラシ属、チョウセンアサガオ属、タバコ属、ナス属、クコ属、 トマト属、バンマツリ属、ホオズキ属、ハシリドコロ属、など |
||||||
| ↓ | キキョウ群: | モチノキ、セリ、マツムシソウ、キク、など | |||||
| 後から分化した植物 (進化した植物 ) | ||
|
| 小石川植物園の樹木 -植物名の由来- 高橋俊一 五十音順索引へ |