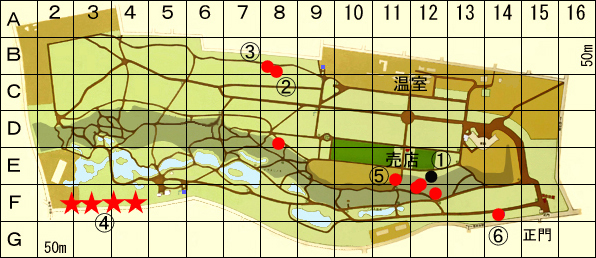| |
| ↑ | 緑藻 : | アオサ、アオミドロ、ミカヅキモ、など | |
| |
| シダ植物 : | 維管束があり 胞子で増える植物 | |
| | | | |
| | | 小葉植物 : | ヒカゲノカズラ、イワヒバ、ミズニラ、など | |
| | | | |
| |
大葉植物(シダ類): |
マツバラン、トクサ、リュウビンタイ、ゼンマイ、オシダなど |
| |
| 種子植物 : | 維管束があり 種子で増える植物 | |
| | | |
| | 裸子植物 : | 種子が露出している | |
| | | ソテツ 類 : | ソテツ、ザミア、など | |
| | | イチョウ類 : | イチョウ | |
| | | マツ 類 : |
マツ、ナンヨウスギ、マキ、コウヤマキ、イチイ、ヒノキ、など |
| | | |
| | 被子植物 : | 種子が真皮に蔽われている | |
| | | 被子植物基底群 : | アンボレラ、スイレン、など | |
| | | モクレン亜綱 : |
コショウ、モクレン、クスノキ、センリョウ、マツモ、など |
| | | | |
| | | 単子葉 類 : |
ショウブ、サトイモ、ユリ、ヤシ、ツユクサ、ショウガ、など |
| | | | |
| | | 真生双子葉類 : |
キンポウゲ、アワブキ、ヤマモガシ、ヤマグルマ、ツゲ、など |
|
以前の分類場所 |
イラクサ目 |
イラクサ科、アサ科、クワ科、ニレ科、など
(イラクサ目はなくなる) |
|
|
ニレ科 |
ケヤキ属、ニレ属、エノキ属、ムクノキ属 (バラ目に移動↓) |
|
| | |
中核真生双子葉類: |
ビワモドキ、ナデシコ、ビャクダン、ユキノシタ、など | |
| | | | | |
| | | | バラ目 群 : | | |
| | | | | バラ亜綱 : | ブドウ、フウロソウ、フトモモ、など | |
| | | | | マメ 群 : |
ハマビシ、ニシキギ、カタバミ、マメ、バラ、ウリ、ブナ、など |
|
|
|
|
|
バラ目 |
バラ科、クロウメモドキ科、ニレ科、アサ科、クワ科、など |
|
|
|
|
|
ニレ科 |
ケヤキ属、ニレ属 |
|
| | | | | アオイ群 : | アブラナ、アオイ、ムクロジ、など | |
| | | | | |
| | | | キク目 群 : | | |
| | | | | キク亜綱 : | ミズキ、ツツジ、など | |
| | | | | シソ 群 : | ガリア、リンドウ、ナス、シソ、など | |
| ↓ | | | | |
キキョウ群: |
モチノキ、セリ、マツムシソウ、キク、など | |
| |