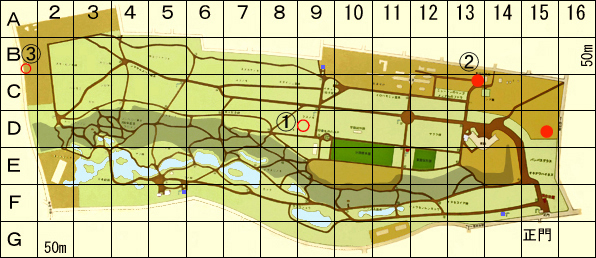| 名前の由来 アオギリ Firmiana simplex |
アオギリ 青桐 : 青い幹の桐 の意味 |
樹皮の緑色がかなり太くなるまで残るところから「青」。
白くて軽い材が「桐」に似ているので「アオギリ」 と呼ばれているわけであるが、材は狂いやすいために、日本ではあまり使われていない。
一部の事典には、葉あるいは葉が茂っている様子が「キリ」に似ていることを理由に挙げているものがある。
もしキリに似ているとしてもあくまで全体のイメージであって、一枚の葉を見てみると 2~4箇所の切れ込みがあり、ホームベース型あるいはハート型のキリの葉とはまるで違う。
また葉に艶があり葉柄も長い、などの違いもある。
『園芸植物大事典』によると、リンネの息子 (1741-1783) が 1781年に、「プラタナスの葉に似た」という種小名 Sterculia
platanifolia を付けているが、これも適切とはいえない。 |
|
| アオギリの葉 |
キリの葉 |
 |
 |
タイルの大きさは 30cm 角
|
| 中国名 梧、梧桐 : |
「梧(ゴ)」には「支える、壮大なさま」の意味があり、そこから「枝葉の生い茂った樹」 アオギリを表すようになった。
古くには「木偏に親」でシンという呼び名もあった。シンは「棺桶」のことで、アオギリが中国での最良の棺桶材とされているためである。
また琴に似た楽器の材料にも使われるために、琴の材料であるキリという名が「梧」に付け加えられ、「梧桐」となった。
アオギリは、大風が吹いてやがて雨が降る時にその葉がゆれて、降雨を告げるとされ、中国古代の人は農耕生活に豊穣をもたらす木と考えた。
その後、大風が「鳳凰」に変化してアオギリはめでたい木とされた。
(おもに『園芸植物大事典』による)
英語の phoenix tree はこれに由来する。
清少納言が枕草子の中で、キリとアオギリを混同した原因である。
|
|
| 種小名 simplex : 単一の、単性の という意味 |
アオギリの花は、一つの花の中に雄しべ・雌しべを持つ「両性花」ではなく、雄花・雌花が別々の「単性花」であるために名付けられた。
雄花・雌花は花序 (花の房) の中に混在している ということである。
雌花がどこに付いているのか、割合はどの程度かなど、細かな観察はしていない。
simplex の最初の命名者はリンネで、このときは Hibiscus属 フヨウ属として分類していた。 これは大きなミスだ! と考えていたら、APG分類では アオギリ属はアオイ科となった・・・。
|
|
| Firmiana アオギリ属 : 人名に由来する |
属名はイタリア北部ロンバルディアの知事であったフィルミアン (K.J.von Firmian 1718-82) の名にちなんでいるということであるが、それ以上の情報は見つからず、フィルミアンが植物学に関係していたのかどうかは不明である。
このアオギリ属を定義したのは、リンネとほぼ同じ時代のジョバンニ・マルシリ (1727-95) が 59才の時である。
マルシリについても情報がないが、おそらくイタリア人のマルシリが、同時代で面識のあるフィルミアンに「献上」したものと思われる。
アオギリ属はおもに南アジアに分布し、世界に9種ないし10種がある。 |
|
|
リンネがアオイ属としてアオギリを命名したのは18世紀中頃、そしてマルシリによって18世紀後半にアオギリ属 (フィルミアナ属) が定義された。
アオギリ属の特徴は果実が袋状となり、さらには種(タネ)が成熟する前にその袋が開いて垂れ下がる点にあり、アオイ属とは大きく異なるにもかかわらず、20世紀初めになるまでの
約 150年もの間、アオギリはアオイ属とされていたことになる。
これには訳がありそうで、一つ考えられるのは、リンネの命名後 間もない 1782年に、リンネの息子が アオギリを
Sterculia platanifolia L. f. (1782)
と命名したものが通用したのではないだろうか。 その50年後に、
Firmiana platanifolia Schott & Endl. (1832)
と アオギリ属に訂正されており、リンネの Hibiscus simplex が忘れられていたのでは? それもおかしな話だが・・・。
platanifolia は、プラタナスのような葉の 意味である。
|
|
| アオギリ科 青桐科 Sterculiaceae : |
世界に約70属 約1,000種があるとされ、チョコレートの原料「カカオ」やコーラ飲料の原料の一つ「コラノキ」が含まれる。
日本ではアオギリが代表的な種であるために「アオギリ科」と呼ばれているが、学名の基準となっているのはリンネが命名したステルクリア属である。
遺伝子配列を分析した結果提案されているAPG分類では、アオイ科に分類される。 アオギリ科だけでなく、シナノキ科・パンヤ科も アオイ科に含まれることになっている。 |
| |
|
| 参考 ステルクリア属 Sterculia Linn. |
| ステルクリア属の和名としては、学名をそのままカタカナにして呼ぶ場合のほかに、「ピンポン属」、「ゴウシュウアオギリ属」がある。 |
|
| ピンポン属 Sterculia属 |
| 愛ちゃんの「卓球」ではなく、ステルクリア属の一種 Sterculia nobilis の中国名「蘋婆(ピンポー)」の音が変化して、「ピンポンノキ」となったものである。 |
|
| ピンポンノキの花 |
ピンポンノキの実 |

果実は熟すと赤くなり、中から直径約2cmの黒い実が出てくる。
白い実であれば、まさに「ピンポンの木」なのだが....
中国南部や台湾では食用として売られていることがあるが、甘味はないとのこと。 |

|
| ゴウシュウアオギリ属 Sterculia属 |
属名Sterculiaは、ローマ神話の便所の神 Sterculius に由来する。ラテン語の stercus は「糞」の意味で、ステルクリア属のある種の花や果実に、悪臭があることによる。
ゴウシュウアオギリ属の漢字は、学名の意味からすると「強臭青桐属」で、臭いの強い、つまり臭いアオギリ属という意味である。
|
|
| 参考 ゴウシュウアオギリ |
ゴウシュウアオギリ Brachychiton acerifolius |
上記「強臭青桐属」と同じ名前なので気になっている。
この 「ゴウシュウアオギリ」 も同じアオギリ科で、ブラキキトン属である。
30m にもなる高木で、オーストラリアの原産であるところから「豪州アオギリ」と名づけたもの、と解釈している。
本種が載っている『週間朝日百科/植物の世界』ではSterculia属の和名を「ピンポンノキ属」としているため、本種を「ゴウシュウアオギリ」としても混乱することはない。
|
|
| ゴウシュウアオギリ |
赤い花 |
 |

|
| 葉の様子 |
花のアップ |
 |
 |
写真はシンガポール植物園で8月上旬に撮影したもの。
落葉期に、軸まで真っ赤な花が咲く。
美しいかどうかは ちょっと疑問...
まだ小さな木で、高さ約6m。
|
|
|