 |
|
|||
| 科 名: | モクレン科 Magnoliaceae | |||
| 属 名: | モクレン属 Magnolia Linn. (1735) | |||
| 異 名: | Magnolia kobushi Mayr (1906) | |||
| Magnolia praecocossima Koidz (1929) | ||||
| 英語名: | kobus magnolia | |||
| 原産地: | 日本全国、韓国 済州島 | |||
| 用 途: | 庭木 |
|||
 |
|
|||
| 科 名: | モクレン科 Magnoliaceae | |||
| 属 名: | モクレン属 Magnolia Linn. (1735) | |||
| 異 名: | Magnolia kobushi Mayr (1906) | |||
| Magnolia praecocossima Koidz (1929) | ||||
| 英語名: | kobus magnolia | |||
| 原産地: | 日本全国、韓国 済州島 | |||
| 用 途: | 庭木 |
|||
| 早春の青空に映える白い花。落葉樹の葉が出る前なので、よけいに目立つ。 |
| ①:分類標本園横 2011.3.29. |
 |
| 北から南方向を見ている。標本園の売店側。管理地の柵内に生えている。 |
| ②:樹 形 2011.4.7. |
 |
| ハンカチノキのすぐ横。この写真も北から南方向を見ている。コブシの後ろがハンカチノキ。 |
| ④:30番通り奥の大木 2011.3.23. |
 |
 |
| 2011.3.27 雲を真っ白 とすると、花は少し黄色がかっている。 高さ 約15m。長径75センチ。 |
| ④:折れた大枝 2012.10.31. |
 |
| 右側に長く伸びていた枝は、2012年9月末の台風で折れたカイノキに引っかけられて、右側に伸びていた大枝が折れてしまった。 |
| ⑤:ハンノキ池 2011.4.1. |
 |
| 20番通り 右側土手。左奥に太郎神社の鳥居が見える。 |
| 幹の様子 | |
 |
 |
| 左:No. ② 右:No. ④ |
| 開花の準備 2009.3.21. |
 |
| 毛で覆われた2枚の托葉に包まれている。間に見えるのは 通常一枚ある「花柄に付く若葉」。 |
| ①:咲きたて 2011.3.29. |
 |
| この年は? 随分黄緑色をしている。 せっかく垂れ下がっていたこの枝は 無くなってしまった・・・・。 |

| 花弁は6枚、直径 10センチ。香りもあったと思うが、記憶にない。 |
| 萼は3枚 |
 |
| 雌しべが先に熟す 2007.3.2. |
 |
| 花弁が9枚 2011.4.7. |
 |
| ハンカチノキ横のこの木は、萼が花弁化して9枚となっている。 栽培品種 あるいは 園芸品種なのだろう。 |
 |
| 花弁の裏が紅紫色できれいだ。 |
| ①:葉の様子 2009.5.5. |
 |
| 波打っているが 全縁。長さ 10センチ前後。 |
| 若い実 2011.7.5. |
 |
| 赤くなった実 1999.9.24. |
 |
| 自身で撮ったデジカメの最初期の写真。画像には修正を加えてある。 |
| コブシの 位 置 |
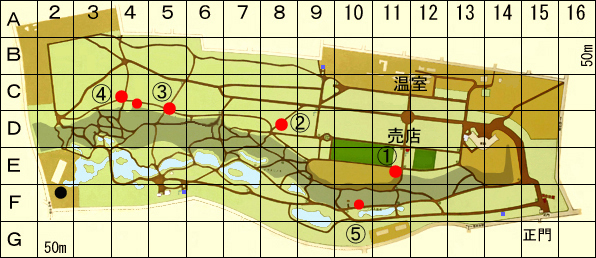 |
| 写真①: | E11 d | ● | 40番通り 標識42からすぐの左側 |
| 写真②: | D8 c | ● | 30番通り 右側。ハンカチノキの横 |
| 写真③: | C5 bd | ● | 30番通り 標識36の手前右 |
| C4 d | ● | 30番通り 標識37の手前 左側 | |
| 写真④: | C4 b | ● | 30番通り 標識37の右側 |
| 写真⑤: | F10 bc | ● | 70番通り 太郎神社手前右側土手 |
| ● | 博物館小石川分館の敷地内 |
| 名前の由来 コブシ Magnolia kobus | ||||||||||||||||
コブシ 拳 : |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 種小名 kobus: nom. cons.(保留名) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 『廻国奇観』845ページ |
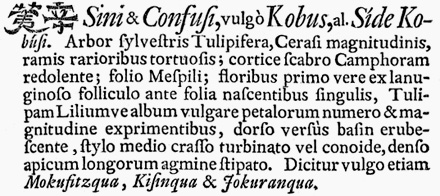 |
|
| モクレン科 Magnoliaceae : 人の名前に由来する | |||
|
| 植物の分類 : | APG II 分類による モクレン の位置 |
| 花の各器官は「葉」が変化したものと考えられている。 モクレン類は 1本の軸の周りに「花弁・雄しべ・雌しべ」が多数付く花の構造が原始的であり、被子植物の中では 早くに分化した植物とされている。 |
| 原始的な植物 |
| ↑ | 緑藻 : | アオサ、アオミドロ、ミカヅキモ、など | |||||
| シダ植物 : | 維管束があり 胞子で増える植物 | ||||||
| 小葉植物 : | ヒカゲノカズラ、イワヒバ、ミズニラ、など | ||||||
| 大葉植物(シダ類): | マツバラン、トクサ、リュウビンタイ、ゼンマイ、オシダなど | ||||||
| 種子植物 : | 維管束があり 種子で増える植物 | ||||||
| 裸子植物 : | 種子が露出している | ||||||
| ソテツ 類 : | ソテツ、ザミア、など | ||||||
| イチョウ類 : | イチョウ | ||||||
| マツ 類 : | マツ、ナンヨウスギ、マキ、コウヤマキ、イチイ、ヒノキ、など | ||||||
| 被子植物 : | 種子が真皮に蔽われている | ||||||
| 被子植物基底群 : | アンボレラ、スイレン、など | ||||||
| モクレン亜綱 : | コショウ、モクレン、クスノキ、センリョウ、マツモ、など | ||||||
| モクレン目 | ニクズク科、モクレン科、バンレイシ科、など | ||||||
| モクレン科 | モクレン属、ユリノキ属、など | ||||||
| 単子葉 類 : | ショウブ、サトイモ、ユリ、ヤシ、ツユクサ、ショウガ、など | ||||||
| 真生双子葉類 : | キンポウゲ、アワブキ、ヤマモガシ、ヤマグルマ、ツゲ、など | ||||||
| 中核真生双子葉類: | ビワモドキ、ナデシコ、ビャクダン、ユキノシタ、など | ||||||
| バラ目 群 : | |||||||
| バラ亜綱: | ブドウ、フウロソウ、フトモモ、など | ||||||
| マメ 群: | ハマビシ、ニシキギ、カタバミ、マメ、バラ、ウリ、ブナ、など | ||||||
| アオイ群: | アブラナ、アオイ、ムクロジ、など | ||||||
| キク目 群 : | |||||||
| キク亜綱: | ミズキ、ツツジ、など | ||||||
| シソ 群 : | ガリア、リンドウ、ナス、シソ、など | ||||||
| ↓ | キキョウ群: | モチノキ、セリ、マツムシソウ、キク、など | |||||
| 後から分化した植物 (進化した植物 ) |
| 小石川植物園の樹木 -植物名の由来- 高橋俊一 五十音順索引へ |