 |
|
|||
| 別 名 : | ハルコガネバナ、アキサンゴ | |||
| 科 名 : | ミズキ科 Cornaceae | |||
| 属 名 : | ミズキ属 Cornus Linn. (1737) | |||
| 漢 名: | 山茱萸 shan zhu yu | |||
| 英 名 : | Japanese cornel | |||
| 原産地 : | 中国、朝鮮半島 | |||
| 用 途 : | 日本には江戸時代中期に薬用植物として渡来した。庭木、盆栽、生け花の材料として使われる。果実酒にも。 薬効は 滋養強壮・腰痛・めまい・耳鳴り、止血などの収斂剤に。 |
|||
 |
|
|||
| 別 名 : | ハルコガネバナ、アキサンゴ | |||
| 科 名 : | ミズキ科 Cornaceae | |||
| 属 名 : | ミズキ属 Cornus Linn. (1737) | |||
| 漢 名: | 山茱萸 shan zhu yu | |||
| 英 名 : | Japanese cornel | |||
| 原産地 : | 中国、朝鮮半島 | |||
| 用 途 : | 日本には江戸時代中期に薬用植物として渡来した。庭木、盆栽、生け花の材料として使われる。果実酒にも。 薬効は 滋養強壮・腰痛・めまい・耳鳴り、止血などの収斂剤に。 |
|||
| 園内には4本のサンシュユがある。開花は3月上旬で、特に梅園の一本は 紅白のウメとのコントラストが美しい。 |
| ①:樹 形 2011.3.13. |
 |
| 梅園内、山側の中央に。樹高 約8m。 |
| ②:70番通り 2012.11.8. | |
 |
|
| 奥を見ている。 ↑サンシュユ ↑トイレ この木も梅園の横にあり、右手が一面の梅の木。 |
| ③:20番通り 2011.3.23. |
 |
| 標識25番の先 左側。ちょうど水飲みの左にある。 タラヨウ ↑ 高さ 約9.5m。 |
| 枝の先に付く花 2001.2.25. |
 |
| 花序は 2対4枚の芽鱗片 (総苞片) に包まれている。開花後も、芽鱗は一定期間 落ちずに残る。 |
| ②:開 花 2000.3.18. |
 |
| ②:満 開 2011.4.1. |
 |
| 花の詳細 2011.3.13. |
 |
| 花弁と雄しべの数は4。萼は小さくて目立たないようだ。 |
| ささくれ立つ樹皮 |
 |
| 新 葉 2011.4.1. |
 |
| 越冬した冬芽は 1対の芽鱗片に包まれていた。葉は対生。 |
| 葉の様子 2012.11.8. |
 |
| 葉脈部分が凹んでいるので、はっきりとした影ができる。側脈(主脈から分かれた葉脈) はどこまでも平行を保つ。葉の色は少し黄色味を帯びてきている。 同じ属のミズキの葉に似ている、と思って較べてみた。 |
| ミズキ と サンシュユ |
 |
| 白いのは葉裏。葉の長さ(葉身)はともに 約14センチだが、葉の形が違うために葉脈の状態も違っている。大きな違いは側脈の数で、ミズキは 10、サンシュユは6。また ミズキの葉柄は長くて元が赤いところも違う。 |
| 若い実 2000.7.27. |
 |
| 落ちた実を葉に載せて 2012.11.8. |
 |
| 鮮紅色という言葉がピッタリの 艶やかな実。生で食べられるが極めて酸っぱい味だ。中央に 中から出てきた核が写っている。 |
| 漢方薬 2012.1.14. |
 |
| 年を越しても枝に残る実も多い。ここまで来れば 漢方薬の「山茱萸」に近い。リンゴ酸や酒石酸 その他の有機酸が含まれるそうで、滋養・強壮をはじめ 色々な薬効があるという。 |
| サンシュユ の 位 置 |
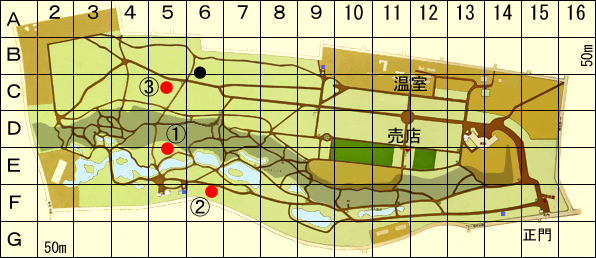 |
| 写真① : | E5 a | ● | ショウブ池の右手、梅園の中央 |
| 写真② : | F6 c | ● | 70番通り 左手 |
| B6 b | ● | 20番通り 標識25番の手前右手、トキワマンサクの裏 | |
| 写真③ : | C5 ac | ● | 20番通り 標識25番の先 左側 |
| 名前の由来 サンシュユ Cornus officinalis | ||||
和名 サンシュユ 山茱萸 : 山に生える 茱萸? |
||||
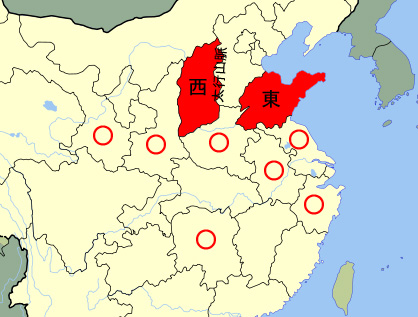
|
||||
| 別名 ハルコガネバナ : 春黄金花 | |||
|
|||
| 別名 アキサンゴ : 秋珊瑚 | |||
|
|||
| 種小名 officinalis : 薬用の、薬効のある の意味 | |||
|
|||
| Cornus ミズキ属 : | ||||||
|
| 植物の分類 : | APG II 分類による サンシュユ の位置 |
| ミズキ目 ミズキ科の位置は APG分類で大きく変わった。 |
| 原始的な植物 |
| ↑ | 緑藻 : | アオサ、アオミドロ、ミカヅキモ、など | |||||
| シダ植物 : | 維管束があり 胞子で増える植物 | ||||||
| 小葉植物 : | ヒカゲノカズラ、イワヒバ、ミズニラ、など | ||||||
| 大葉植物(シダ類): | マツバラン、トクサ、リュウビンタイ、ゼンマイ、オシダなど | ||||||
| 種子植物 : | 維管束があり 種子で増える植物 | ||||||
| 裸子植物 : | 種子が露出している | ||||||
| ソテツ 類 : | ソテツ、ザミア、など | ||||||
| イチョウ類 : | イチョウ | ||||||
| マツ 類 : | マツ、ナンヨウスギ、マキ、コウヤマキ、イチイ、ヒノキ、など | ||||||
| 被子植物 : | 種子が真皮に蔽われている | ||||||
| 被子植物基底群 : | アンボレラ、スイレン、など | ||||||
| モクレン亜綱 : | コショウ、モクレン、クスノキ、センリョウ、マツモ、など | ||||||
| 単子葉 類 : | ショウブ、サトイモ、ユリ、ヤシ、ツユクサ、ショウガ、など | ||||||
| 真生双子葉類 : | キンポウゲ、アワブキ、ヤマモガシ、ヤマグルマ、ツゲ、など | ||||||
| 中核真生双子葉類: | ビワモドキ、ナデシコ、ビャクダン、ユキノシタ、など | ||||||
| バラ目 群 : | |||||||
| バラ亜綱: | ブドウ、フウロソウ、フトモモ、など | ||||||
| 以前の分類場所 | ミズキ目 | ウリノキ科、ニッサ科、ミズキ科、ガリア科 | |||||
| マメ 群: | ハマビシ、ニシキギ、カタバミ、マメ、バラ、ウリ、ブナ、など | ||||||
| アオイ群: | アブラナ、アオイ、ムクロジ、など | ||||||
| キク目 群 : | |||||||
| キク亜綱: | ミズキ、ツツジ、など | ||||||
| ミズキ目 | ミズキ科、ヌマミズキ科、シレンゲ科、アジサイ科、など | ||||||
| ミズキ科 | ウリノキ属(←ウリノキ科 より)、ミズキ属 | ||||||
| シソ 群 : | ガリア、リンドウ、ナス、シソ、など | ||||||
| ↓ | キキョウ群: | モチノキ、セリ、マツムシソウ、キク、など | |||||
| 後から分化した植物 (進化した植物 ) | ||
|
| 小石川植物園の樹木 -植物名の由来- 高橋俊一 五十音順索引へ |