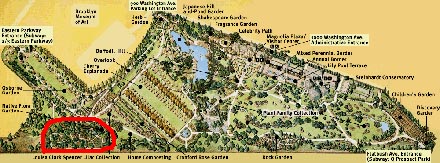樹木を中心に掲載しているが、とてもきれいに咲いていたので、カタクリの仲間を紹介したい。
マンハッタンからイースト・リバーを渡ったブルックリンの植物園。
その中で 「ネイティブ・フローラ・ガーデン」は、ニューヨーク首都圏に自生する草花を集めて落葉樹の林に植栽したエリアで、林の間を細い遊歩道が縫っている。
|
| ネイティブ・フローラ・ガーデンの位置 |
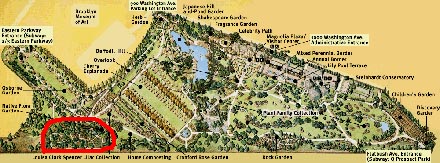 |
地図はブルックリン植物園のホームページより
|
| 4月9日 レンギョウが満開 |
 |
|
残念ながら、これはネイティブ・フローラ・ガーデンの隣の区域の写真なのだが、東京の季節感より半月遅い感じで、園内は黄水仙や連翹・木蓮が満開で、ソメイヨシノはまだまだ
だった。
|
|
|
風もなく深とした林の中、ピンオーク(アメリカガシワ)やアカガシワの枯れ葉の間に群生していた。
通常2枚の葉が付いていて、それぞれ花はひとつである。
|
| 茶色の斑紋がカタクリ属の特徴 |
 |
|
アメリカカタクリの斑紋には、よく見ると 褐色の部分と白 (灰色) の部分があり、本来の緑色の部分は むしろ少ない。
|
 |
開くと花弁が反転するが、日本のカタクリほどではない。
花のサイズは、開いた状態で直径5cm ぐらい。
雄しべの葯が黄色いものと褐色のものがあるが、初め黄色で、葯が開くと褐色になるように思われる。
詳しくは観察しなかった。
|
| 名前の由来 アメリカカタクリ Erythronium americanum |
アメリカカタクリ : アメリカ原産のカタクリ の意味 |
| 『園芸植物大事典』、『植物の世界』、ともに和名がないので一応「仮名」であるが、種小名からしても、アメリカカタクリしか考えられない。 |
|
| 種小名 americanum : アメリカの という意味 |
|
|
| 英語名 : |
アメリカ原産だけに、いくつかの英語名がある。
amberbell : 琥珀色のベル
外花被片の外側が褐色であるため、咲き始めはツートンカラーが可愛らしい。 |
 |
trout lily : 鱒ユリ |
葉の褐色の斑紋を、魚のマスの模様に見立てたもの。
|
|
|
| yellow adder's-tongue : |
adder は「マムシ、毒蛇」である。
「黄色い舌」は、内花被片のことなのか、黄色い雄しべを指すのか。
|
|
|
以下は 『園芸植物大事典』の属名の項に記載されていたもの。
dog-tooth violet : 犬歯スミレ (dogtooth violet) |
花はスミレよりもかなり大きいが、細長い花弁を犬歯(糸切り歯)に例えたものであろう。
|
|
|
| fawn lily : 鹿の子ユリ ( fawn : 子鹿 ) |
| 葉の斑紋を、シカのまだら模様にたとえたもの。 |
|
奈良公園のシカ
オス
ただし 子鹿ではない
|
 |
カノコユリのカノコを「カノコ絞り」の模様にちなむ、と書いてある事典があったが、染め物の技術が進展したのは名前が付いた時よりも、ずっと後年(近年)のことでしょう。
|
|
| Erythronium カタクリ属 : Linn. (1735) |
ギリシア語で「赤」の意味の erythros に由来する。
本種などの黄色の花ではなく、ヨーロッパ原産の種 (シュ) に基づいているようだ。
その後に発見されたものは白や黄色の花の方が多く、赤は少数派になってしまった。
属名に 色にちなむ名前を付ける時には、注意が必要ということ。
|
|
| ユリ科 Liliaceae: |
これも色にちなむ名である。
世界でもっとも古くから栽培されていて、キリスト教のマリアのシンボルでもある、マドンナ・リリー (Lilium candidum) に付けられたギリシア名
leirion と同じ意味を持つ、ラテン古名が lilium であったことによる。『園芸植物大事典』
ケルト語で li が白の意味を表す。
ユリはかなり寒い地方も含めて、広く世界中に分布しており、日本でも古事記や日本書紀にも登場している。
しかし、百合の花の色も、白のほかに 黄・橙・朱・赤・ピンクがある。
|
|
|
アメリカカタクリ |
| ← カタクリ (片栗) Erythronium japonicum Dence. (1854) |
|
| 日本、朝鮮半島、サハリンに分布する。 |
|
カタクリ |
4月2日
京都植物園
|

|
| 褐色がはいっている葉は少なく、ほとんどの斑が白であった。 |
|
 |
 |
事典にはカタクリの古名「カタカゴ」についての記載がある。
『園芸植物大事典』では カタカゴ (傾籠)。
”傾いた籠状の花という意味であるといわれる”と解説されている。
『植物の世界』ではカタカゴ (堅香子)となっており、由来の説明はない。 大伴家持の歌の用例が出ている。 |
| もののふの 八十乙女らが汲みまがふ 寺井のうえの 堅香子の花 |
| 歌の状況の勝手な解釈 |
たくさんの若い女が 寺の井戸で争うように水を汲みあっている。
井戸につづく森の斜面には、清楚なカタクリの花が 賑やかに咲き、春の木漏れ日に揺れている。 |
|
カタクリは、”どちらかというと寒い地域の日陰や半日陰地で、排水の良い腐葉土を好む。本州中部以西での栽培は難しい” と事典にあるので、奈良の政治家であった大伴家持が実物を見る機会は、ないとは言えないが 少なかったのではないだろうか。
でも 昔は奈良も もっと寒かったかも知れない。
|
|
|
カタカゴ |
そこで 「カタカゴ 傾籠」の由来であるが...。
確かにカタクリの花の茎は少し傾いている。さらに 花も花茎に対して傾いて咲いている。
そして 反っくり返った状態の花が「籠」に見えないこともない。
しかし、この花を見て「傾いた籠」という名を付けますか?
意味はともかくとして、万葉集でも「カタカゴ 堅香子」と使われているのであれば、「カタカゴ」と発音されていたのは間違いないであろう。
問題は「堅香子」の漢字をそのまま受け取っていいのかどうかだ。
「香」という字が使われているが、カタクリの花が匂うのかどうかは事典に記載がない。
植物園では大抵が立ち入り禁止の区域で栽培されているので、近づいて花の匂いを嗅ぐことができない。
そして結局、堅香子の意味もわからない。
|
|
|
カタ鹿子 |
私の考えは、
「カゴ」という言葉は、英語名にもあるように、「鹿子」ではないかと思っている。
緑の葉に、茶色あるいは白い斑がはいっているようすである。
では「カタ鹿子」の残りの「カタ」は?、というと、うまい解釈が見つからない。
何が傾いているのか? あるいは 何が堅いのか? |
|
| * * * |
|
後になって、Wikipedia の記述を読んで気が付いた!
カタクリの生態の 葉についての記述である。 |
|
・種子から芽生えた1年目は「細長い糸状」
・2年目から7〜8年程度までは、卵状楕円形の「一枚の葉」
・花を咲かせる年になって 初めて「二枚の葉」になる |
|
| ということは、花を付けていない「片側だけの鹿の子模様の葉」がたくさんあるということで、これが「片鹿子 カタカゴ」の由来ではないだろうか。 |
|
|