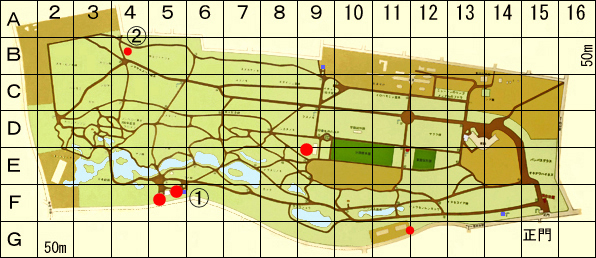| 名前の由来 ビワ Eriobotrya japonica |
ビワ : ビワの実が楽器の琵琶に似ているところから |
ビワの名が名付けられたのは、昔々の中国でのことであって、和名としてのビワは、漢名の枇杷の音読み「ピパ」(正確な音は不明)に 「比波」の字を当てたものが「ビワ」に転訛したものと思われる。
|
|
| 種小名 japonica : 日本の という意味 |
1775年に来日したツュンベリー (リンネの弟子) が、日本で採取したビワに対して名付けたものである。その時に分類した属名は Mespilus属
セイヨウカリン属であった。
その後、ロンドン大学植物学教授で、英国王立園芸協会の要職を歴任した英国を代表する植物学者である、リンドレイ(1799-1865)
がビワ属を定義した。
|
|
| Eriobotrya ビワ属 : |
東アジアに約26種が分布しており、「ビワ」以外には、台湾ビワ、雲南ビワ、大花ビワなどがあるが、いずれも果実は小さい。
学名はギリシア語の erion (羊毛) と botrys (ブドウの房)に由来する。
事典によっては「房状の果実による」とある。 現在の栽培品種では「ひと房」のビワの数はそれ程多くないために、「ブドウの房」のイメージは無いが、命名時の野生種は小さな実がたくさん生っていた可能性もある。
確かにビワの実は細かい毛で覆われているが、 「羊毛に包まれている」というイメージではない。
私は、白い毛に包まれた「ビワのつぼみ」に由来しているという説に賛成である。 |
|
 |
 |
| |
| ビワ に関する メモ |
ビワ 琵琶 : |
ビワの名は果実の形が楽器の琵琶に似ているために付けられたという。
それでは楽器の「琵琶」の名の由来はなんであろうか?
琵琶の起源はペルシアの古い楽器バルバット barbat や ビバットにあるといわれ、西アジアからアラビア商人によって広く伝播し、ヨーロッパではリュートからギターヘ、東洋では琵琶となり、日本には奈良時代に中国から渡来した。 |
|
|
いろいろな琵琶 |
現在の日本の琵琶は雅楽で使われる楽琵琶、小型の盲僧琵琶、薩摩琵琶(図 上)、筑前琵琶(図2番目)、薩摩と筑前を融合した錦琵琶(図3番目)、平家琵琶などがあるが、いずれも曲がった棹と洋ナシ形の胴をもち、黄楊(ツゲ)で作った撥(バチ)で弾いて演奏する撥弦楽器である。
弦は4本が多いが、5弦のものもある。
図の一番下は中国の琵琶で
「ピパ」または「ピーバ」と呼ばれ、柱(ジ)(フレット)が半音階にたくさん並んでいる。ばちを使わずに指に爪をつけて演奏する擦弦楽器である。 |

小学館『万有百科大事典』より |
|
| この演奏で弦を手前から外の方に弾くのを「琵」といい、逆向きを「琶」というところから琵琶の名前がついたといわれている。 |
別の説としては、ササン朝ペルシア(3〜7世紀)のバルバットやビバットの呼び方に関連する、というものもある。
いずれにせよ琵琶の形は唐の時代(7〜9世紀)にはすでに整っていたようだ。 |
|
一方樹木のビワの方は、中国では最も古くから栽培されていた果物の一つであり、6世紀の書物『広志』にはビワの黄肉種と白肉種の記述があるという。
とすれば、西方から琵琶が伝わる前から利用されていて、別の名前で呼ばれていた可能性もある。
何しろ大昔の中国での話であるため、琵琶がいつ頃中国に伝えられたのか、そしてビワの名前がいつ頃から「ピパ(枇杷)」と呼ばれるようになったのか、以上の資料ではははっきりとしない。
|
|
|
茂木と田中 |
日本でも果物として古く奈良時代から利用されていたようであるが、実が小さく、果肉も薄かったため、栽培されるまでにはいたらなかった。
江戸末期天保・弘化年間(1830〜48)になって、中国南部で栽培されていた、実が大きくて果肉の厚いビワの種が長崎に伝えられた。長崎県のホームページによると、三浦喜平次の妹シオが出島からその種を持ち帰り、現在の北浦町の畑に播いたのが「茂木ビワ」の始まりといわれている。
種を蒔き、大きな実の品種を選んで育てることを繰り返し、また明治から大正にかけて袋かけや肥料、剪定などの技術改善も行われて、長崎県は現在でも全国の出荷量の約3分の1を占めている。
もう一つの品種「田中」は、明治12年(1879年)長崎に旅行した博物学者の田中芳男が大きな実のビワに感心し、種を東京に持ち帰って文京区に播いたものの中から得られたという。
果実の形が茂木に比べて丸みを帯び、やや酸味が強いが実の数は多い。 千葉県や伊豆地方が中心である。
ビワは花が咲くのが11月から2月、実が熟すのが6月であるため、冬が温暖な地方が適している。
|
|
|
ビワは種ばかり? |
ビワは真ん中に大きな種があるために、食べるところが少ないと思われがちであるが、実際の果肉の体積は67〜70%となっている。
日本食品標準成分表によると他の果実の可食部は、伊予柑、八朔 60%、スイカ
60%、みかん 75%、バナナ 62%である。(体積比か重量比かは不明)
ビワはバナナより食べるところが多い果物ということになる。
また、びわ1kgを果肉と皮と種に分けると、果肉680g(68%)、皮170g、種150gとなるそうで、種は重量比ではわずか15%である。意外にびわの種子は小さい、いや、軽いことがわかった。
(長崎県農林部のホームページ より)
バナナについては自分で確認してみたが、可食部の重量比は61%であった。もちろんバナナの大きさ、品種によって違ってくる。
|
|
|
ビワの効用 |
びわの種子には、アミグダリンというビタミンB17になる成分が含まれており、杏仁水の代用(ビワ仁水)として鎮咳、去痰に用いられた。
食べたビワの種子を2つ割りにしてホワイトリカーに漬ければ3ヶ月ぐらいで「びわ種酒」ができ、その薬効にあずかれるということである。
葉をよく乾かして煎じた「ビワ葉湯」を飲用すると、鎮咳、利尿の効果があり、この煎汁で湿布したり、ビワ葉のはいった風呂に入ると皮膚病に効くという。 江戸川柳に、
枇杷と桃、葉ばかりながら 暑気払い
というものがある。「そう言っては何ですが、葉っぱばかり」ということで、当時のビワの実が小さくて重用されなかったことを示している。
しかし 葉を煎じた「枇杷葉湯(ヨウトウ)」は、江戸時代の中頃から明治の中頃まで、夏の風物詩として流行し、「寝冷え知らず、暑気払い、胃の薬、肺の妙薬」と呼び回って湯を売り歩いたという。
現在でも、高知の日曜市で細かく刻んだ枇杷葉を売っているのを見かけた。 |
 |
|
|
もうひとつの「モモ」についても 同じく「葉ばかり」となっているのは、このモモが現在の水蜜桃とは違う 実の小さい「モモ」、すなわち、現在の「ヤマモモ」ということになる。
|
|
|
| 小石川植物園の樹木 −植物名の由来− 高橋俊一 五十音順索引へ |
|
| 世界の植物 へ |