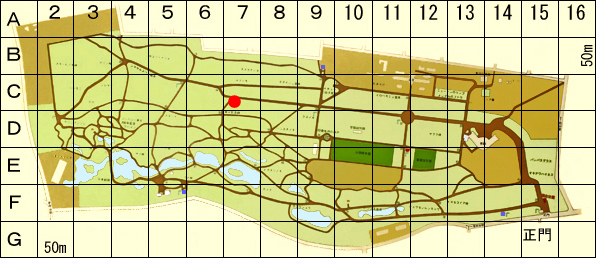| 名前の由来 ハリギリ Kalopananax septemlobus |
ハリギリ 針桐 : トゲのあるキリ の意味 |
キリの名が付いた由来として「葉がキリに似ているため」としている事典や図鑑が多い。
『新訂 牧野新日本植物圖鑑』のハリギリの項にも「葉が大きいことをキリに見立て、枝に針があることを述べた名」とある。
しかし、ハリギリの葉は、形も 枝への付き方も キリとは”まったく”似ていない。
部分的なイメージや木全体のイメージも異なる。 時に、キリは驚くほど大きな葉を付けることがあるが、ハリギリはそういうこともない。
ここは「材がキリ似ているため」とすべきである。
|
|
| ハリギリの葉 |
キリの葉 |
 |
 |
別名 セン、センノキ : |
建築関係ではハリギリのことをもっぱら「セン」と呼んでおり、材を薄くスライスして、合板の表面に張った突き板に加工して内装材にする。また建具・家具・器具材として広く使われている。
着色塗装するとケヤキと区別が付かないほどになるため、その代用品としても使われる。
|
 |
| センノキ 左:板目 右:柾目 |
センの漢字は「栓」または「櫼」と書き、「仙」と書くこともある。
いずれも「セン」の音の漢字を当てたもので、センノキ の由来ははっきりしない。
無数に実が生るので「センナリノキ」 はどうか? |
|
櫼 セン の字について |
「櫼」の字は くさび の意味で、ATOK の文字パレットにはあるのだが、漢字水準は ”該当しない” となっており、『漢和中事典/角川書店』には載っていない。
そこで図書館に出向いて、『大漢和辞典』(諸橋轍次 著/大修館書店/平成11年修訂第2版) を調べた。 12巻をなす大辞典だけあって、さすがに
載っていた。
読み : セン、シン、サン
字義 : ① くさび、 ② とがた、ますがた、 ③ 木の名 すぎ
であった。 ③の出典として、北宋時代 1008年の書物『廣韻』、同じく 1039年の『集韻』が挙げられている。
現在の日本のスギとは種類が違うかもしれないが、ある種の 「杉 すぎ」 であり、くさび型の樹形に由来するものだろう。
とすれば、「櫼 セン」の字を ハリギリに当てるのは、誤用となる。
|
| 秋 田 杉 |
 |
|
なるほど、くさびの木 である。
ちなみに、旁の「韱 セン」の字義は 山ニラ、細い、の意だった。
『廣韻』 や 『集韻』 以前の書物、例えば日本の本草書の源である『本草和名』(901-923年)、およびその手本である唐の『新修本草』(659年撰)なども調べないと、おおもとの由来はわからないのかもしれない。
なお、「櫼」の字には楔(くさび)の意味もあるわけで、刺のあるハリギリを「楔の木」と呼んだ可能性はある。 ただ、くさびの特徴は、一定の割合で 先が細くなる事、あるいは 二つの物を繋ぎ止める役目であり、ベースは長いが 急に細く尖る、ハリギリのトゲの形状とは違う。 これを「楔の木」と呼ぶことは疑問である。 |
 |
|
種小名 septemlobus : 7つに裂けた という意味 |
通常の葉が7つに裂けている状態を表している。
前出の葉の写真のように、小さなものでは 5裂 ないし 6裂もある。 |
|
ハリギリ属 Kalopanax : |
ギリシア語で「美しい」という意味の kalos と、同じウコギ科のトチバニンジン属 Panax を合成したものである。
(葉が)美しいPanax属 という事になるが、ハリギリの葉はあくまで一枚の葉に切れ込みが入った「単葉」であるのに対して、「トチバニンジン 栃葉人参」の葉はその名の通り
トチノキの葉のように葉が分かれている「掌状複葉」で、形は違う。
「トチバニンジン」の方の名は極めて適切な名だと思うが、ハリギリ属はハリギリ一種のみの 「単型属」であるから、 Kalopanax の名は、ハリギリ専用である。
下の二枚の見較べた結果だが、私だったらハリギリの属名として「美しいトチバニンジン属」 とは付けない。
|
|
| ハリギリの葉 |
Panax トチバニンジンの葉 |
 |
 |
右 トチバニンジンの写真
春日健二氏
(kasuga@mue.biglobe.ne.jp)
のホームページ『日本の植物たち』
の中からお借りした。
|
なお Panax の由来は、ギリシア語 pantos すべての + akos 治療 で、オタネニンジン・朝鮮人参などに 薬効があることから。 |
|
ウコギ科 五加木 科 Araliaceae : |
ウコギ科の基準属 Aralia はタラノキ属である。
Aralia はカナダでのフランス語の名、aralie から付けられた と事典にあるが、その意味の解説はない。
タラノキには、ハリギリよりもっと細くて尖った刺が無数に付いている。 |
|
| タラノキの葉 |
タラノキの幹 直径4cm |
 |
 |
ウコギ科は 高木・低木・つる植物・多年性草本もあるグループで、熱帯から温帯にかけて広く分布し、約70属、約700種がある。
多くの共通点は枝、茎、葉に刺があること、小さな花が枝先に多数集まって咲くこと (散形花序) 、葉に切れ込みがあったり羽状・掌状であること。
ウコギの和名は中国名の「五加」の唐音 " ウコ " と、「木」の日本読み "キ" とからなるが、「五加」が名付けられた由来は分からない。
形態上の特色である五数性 (花びらの数が5枚、あるいは5の倍数)に関係しているのだろう。
|
|
| 参考 ハリギリの別名 |
イイギリと同じように日本に分布し、有用材として使われてきたハリギリにも様々な別名・地方名がある。
標準和名のハリギリという名前は後から便宜的に決められたものであり、各地の人々にとってはそれぞれの呼び名がその木の名前である。
|
| テングノハウチワ、テングッパ : 天狗の葉団扇 |
浅く切れ込んだ大きな葉を、天狗の葉団扇に見立てたもの。
|
|
| ヤマギリ : 山桐 |
里で育てられるキリに対して、山に生えるキリの意味。
|
|
| イヌダラ : 犬楤 |
タラノキの芽と同様に若芽また若葉を食用とするが、山菜の王者と呼ばれるタラノキよりも 味が劣るため。
|
|
| エンダラ : (長野、岐阜) |
|
|
| ボウダラ : 棒楤 |
タラノキを始め、普通の樹木は枝の先端が次第に細くなるが、ハリギリの枝は、1年目の枝も太い棒状となるため。
|
|
| バラ : 薔薇(山梨、静岡) |
ハリギリのトゲを、同じように強烈なトゲを持つバラにたとえたもの。
|
|
| イモギ : 芋木(石川) 由来 不明。 |
| シシダラ : 獅子楤(徳島、高知、愛媛) |
タラノキのトゲは細くて長めだが、ハリギリは太く短い。どちらが獅子とは言いかねる。
|
|
| ヤツメダラ : 八つ手楤(佐賀) |
ハリギリの切れ込んだ葉をヤツデの葉にたとえた「ヤツデダラ」が転化したものであろう。 タラノキの葉は二回複葉である。
|
|
| アユシニ : (アイヌ) 刺が多くある木の意味。 |
|
|
| トピックス ハリギリの学名について |
| 研究者の見解による違いで、ハリギリの学名として |
|
Kalopanax septemlobus Koidzumi
Kalopanax pictus Nakai |
|
| のふたつの学名が使われている。両者の元の名前の(事実上の)命名者は、18世紀に日本にやってきた「カール・ツュンベリー」である。 その 元の命名は |
|
Acer septemlobum
Acer pictum |
|
であり、日本で採取 あるいは入手した標本 768種に対して、帰国後の1784年に『日本植物誌』に記載したものに含まれている。 (実際の日本産植物は約530種だった。)
『リンネとその使徒たち/西村三郎』
後にハリギリは、Acer属から ハリギリ属に分類し直された。
牧野博士も間違えてしまった ハリギリの学名については、長くなるために 「 別 項 」にまとめた。 |
|