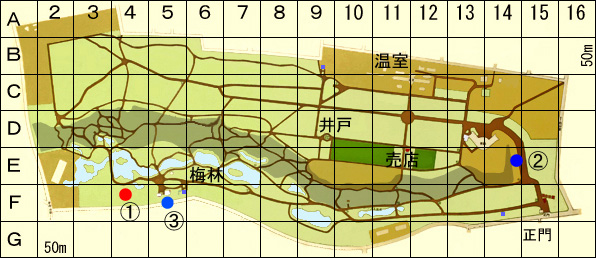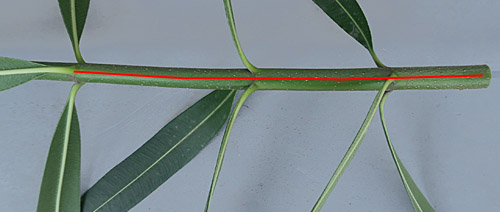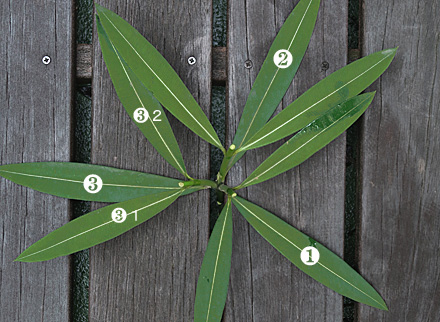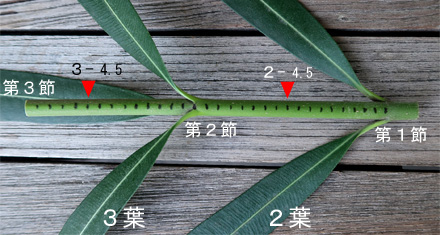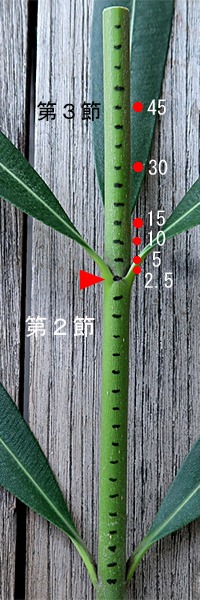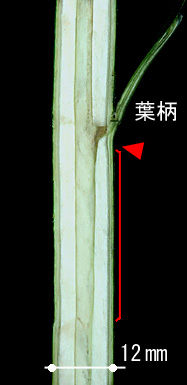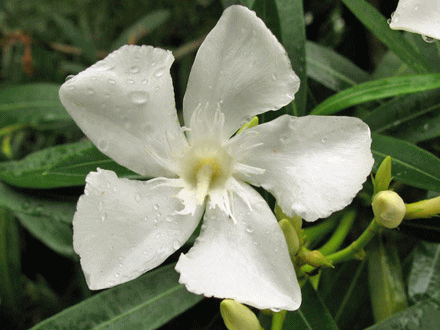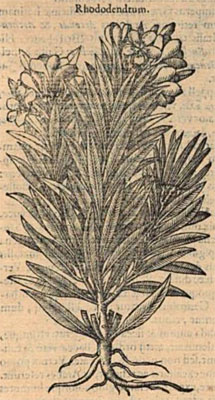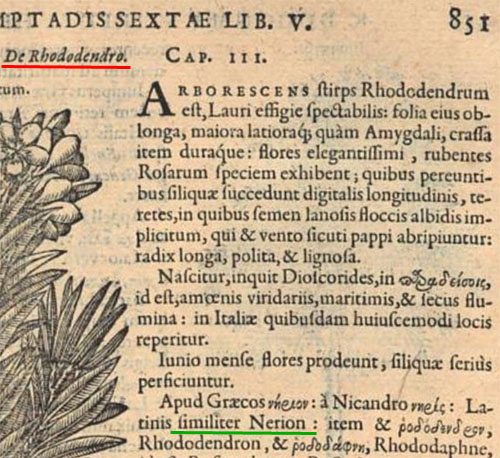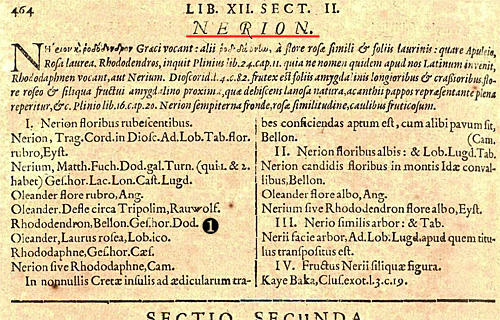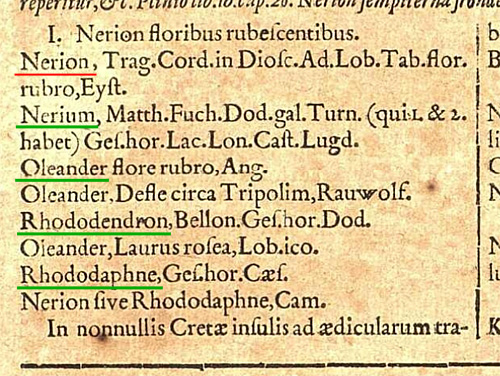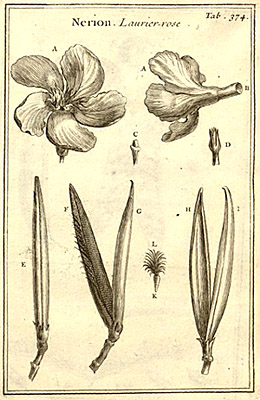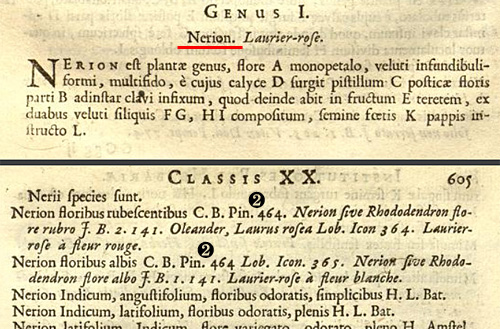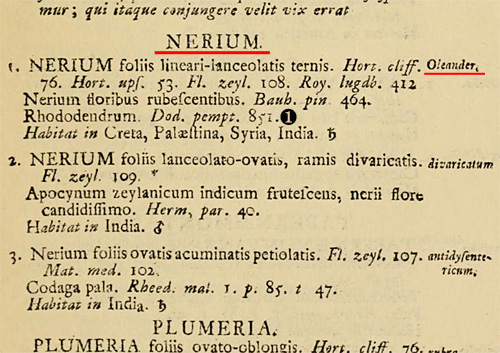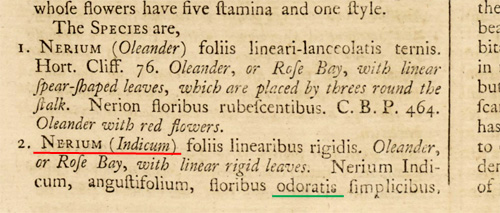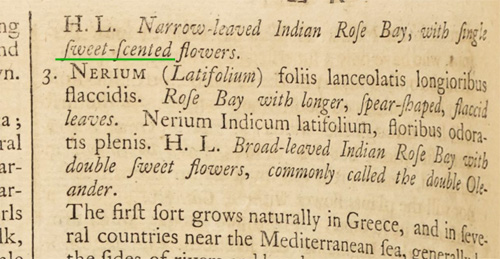| 名前の由来 キョウチクトウ Nerium oleander |
|
| キョウチクトウ:夹竹桃 |
|
中国名の音読み。キョウチクトウは中国雲南省に自生するため、『Flora of China』に載っているが、名称は「欧州夹竹桃」となっている。 |
|
|
|
現在の日本の表記では「夾」だが、中国語では「夹 jiā」が普通で、その意味は『小学館 中日辞典』によると、
1. 挟む、 2. わきに抱える、3. 二つの物の間にある、
4. 入り交じる、 5. 物を挟む道具
であり、「夹竹桃」の用例もある。
今まで何となく「狭い」という意味だと思っていたのだが、間違っていた! |
|
|
|
改めて 夹竹桃 の由来を確認すると、吉田金彦『語源辞典/植物編』に、中国の本『群芳譜』に、「夾竹桃、花五弁、弁微尖、淡紅嫡豔、類(二)桃花(一)、葉狭長類(レ)竹、故名(二)夾竹桃(一)」という説明があり、「花は桃、葉は竹に似ているので
夾竹桃の名となった」ということである。つまり「夹」の意味は『中日辞典』の4.に近い。 |
|
| 属名 Nerium:ギリシア語 neros 湿った に由来する |
|
牧野富太郎の『植物學名辞典』には「neros 湿りたる」しか書かれていないので意味がわからなかったが、前出『語源辞典』に属名の解説も載っていた。
曰く「ギリシア人がキョウチクトウが湿気を好む木だと思いこみ、nerion と呼んだため」とのこと。後半の「命名物語」にも登場する。 |
|
| 種小名 oleander: ? |
|
由来がはっきりしない。
Merriam-Websterによると「中世のラテン語で、恐らく arodandrum、lorandrum あるいは ラテン語 rhododendron
の変化したもの」とある。 |
|
|
|
リンネ以前には、rhododendron がキョウチクトウの名のひとつとして使われていた。後半の「命名物語」参照。 |
|
| キョウチクトウ科 Apocynaceae: |
| キョウチクトウ科の基準属は アポキヌム属 Apocynum Linn. (1735) で、牧野の『植物學名辞典』には apo (離れて) +kyon (犬) とある。これでは意味がわからない。 |
|
「離れて」は果実がふたつに分かれることを指すものかと思ったが、まるで違っていた。
Wikipedia に "away dog" という言葉があり、かつて(大昔に)キョウチクトウ科の dogbane (Cionura erecta) が、野犬除けの毒薬として使われたことによる、とあった。 |
|
| アポキヌム属は基準属となっているにもかかわらず、キョウチクトウ科を代表するようなポピュラーな属ではない。日本には「バシクルモン」という、変わった名前の多年草がある。 |
|
バシクルモン |
北海道から新潟県にかけての日本海側に分布。外国語のような名前は、アイヌ語の「パスクル(カラス)」と「ムム(草)」に由来する 『植物の世界』 とあるが、ピンクのかわいらしい花なので、カラスには不似合いである。
別名 オショロソウ。 |
 |
Apocynum venetum Linn.
var. basikurmum H.Hara |
写真は 春日健二氏のホームページ「日本の植物たち」
(kasuga@mue.biglobe.ne.jp)の中からお借りした。 |
|