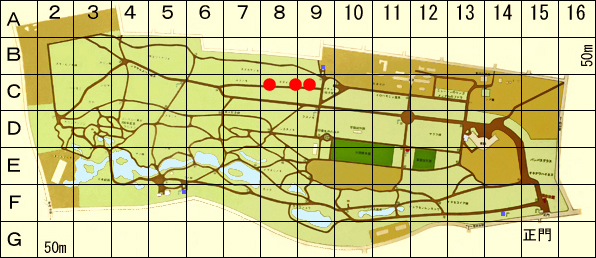| トピックス |
仏教の三聖木 |
仏教の開祖ブッダの「生・悟り・死」に関わりのある3つの木、
「ムユウジュ」、「インドボダイジュ」、「シャラソウジュ」
を 三聖木という。 |
|
・ ムユウジュ 無憂樹 : この木の下で生まれた |
Saraca indica Linn. (1767)
ジャケツイバラ科ムユウジュ属。 原産地はインドからミャンマー。
紀元前5世紀(一説に紀元前6世紀)にサーキヤ(Sakiya)族の国王の長男として生まれたゴータマ・シッダールタ、後のブッタ。
伝えによると、懐妊中の母マーヤーが現在のネパール国にあるルンビニーで、この木の花を見て右手でひと枝折ろうとした時に、右脇腹から生まれたという。 |
|
| ムユウジュ |
ムユウジュ属の一種 |
 |
 |
名札がなくて種は不明
|
|
もとの名を「アショカジュ」または「アシュカジュ」という。 asoka はサンスクリット語で「憂いのない」という意味であるところから、無憂樹と漢訳された。和名はその音読みである。
なお、無憂樹の学名は Saraca asoca W. J. Wilde (1968) だという説も多い。 |
|
・ ボダイジュ菩提樹(和名:インドボダイジュ):
悟りを開いた |
当時の風習によって16歳で結婚し、豊かで平穏なくらしをしていたが、29歳の時に一切を捨てて出家する。激しい苦行を行ったが目的は達せられず、ブッダガヤの「インドボダイジュ」の下に座って思索にふけり、ついに悟りを開いた。
Ficus religiosa Linn. (1753) クワ科 イチジク属
本項 菩提樹の由来 参照。 |
|
・ シャラソウジュ 沙羅双樹 : 80歳で入滅した |
悟りを開いたあとの45年間、ブッダはインド各地で教えを説いて廻ったが、ついに クシナガラの郊外で入滅する。
そこには東西南北に2本ずつのシャラ(沙羅樹)が生えていたということから、この木を「沙羅双樹」と呼ぶようになった。
シャラはサンスクリット語のシャーラ salaで、優れた木、堅固な木の意味である。沙羅はその音を漢字に写したもの。
サラソウジュ、シャラノキ などとも呼ばれる。
Shorea robusta Gaertn. f. (1805)
フタバガキ科シャラソウジュ属
私は日本の温室でしか見たことがない。 |
|
| シャラソウジュ |
幹 |
 |

|
15cm程の幹だが、割れ肌となっている。
新宿御苑 温室 |
| 下から見上げた葉 |
葉のアップ |
 |

|
|
なお、日本で一般に「シャラノキ」と呼んで寺院に植えられているものは、ツバキ科の「ナツツバキ」であり、これまた シャラソウジュとは全くの別物である。
温帯地域ではインド原産のシャラソウジュが育たないため、ボダイジュの時と同じように、代用品としてナツツバキが選ばれたのかも知れないが、外見上の共通点はまったく見あたらない。 |
|
| ナツツバキ |
はげ落ちる幹 |
 |

|
|
|
|
| 小石川植物園の樹木-植物名の由来- 高橋俊一 五十音順索引へ |