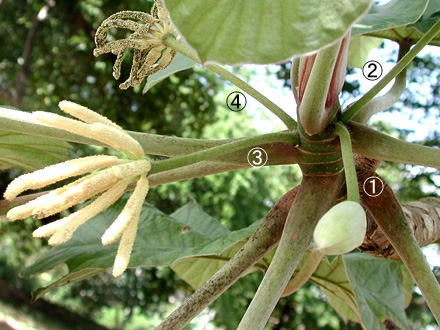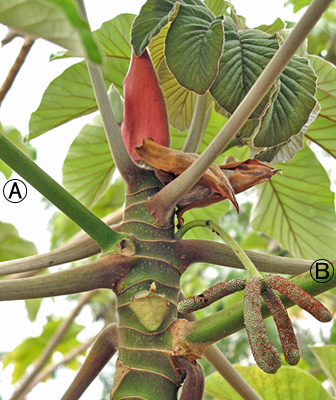|
||||
 2006.10.2 雄花 |
科 名: | イラクサ科 Urticaceae | ||
| 旧科名: | ケクロピア科 Cecropiaceae C. Berg. (1978) |
|||
| 属 名: | ケクロピア属 Cecropia Linn. (1758) | |||
| キューバ名: | Yagruma | |||
| スペイン名: | yagrumo (現地名による) | |||
| 原産地: | メキシコ南部、中央アメリカ、西インド諸島、南アメリカ北部、コロンビア | |||
| 用 途 : | 極めて成長が速く、パルプ用に栽培されることがあるという。 葉は喘息を緩和する薬となる。 |
|||
| 備 考: | 雌雄異株、アリ植物。 一時期ケクロピア科がたてられたが、現在は元のイラクサ科となっている。セクロピアとも呼ばれる。 |
|||
| 撮影地: | ドミニカ共和国 | |||