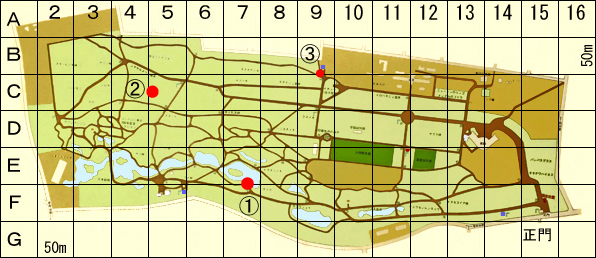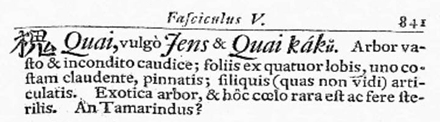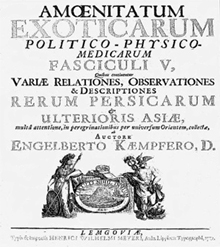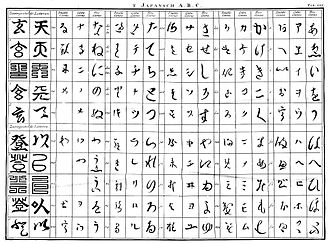|
|
|||
| 科 名 : | マメ科 Fabaceae | |||
| 属 名 : | クララ属 Sophora Linn. ( 1742 ) | |||
| 英語名 : | Chinese scholar tree , Japanase pagoda tree |
|||
| 中国名: | 槐樹、 槐 huai | |||
| 原産地 : | 中国北部 | |||
| 用 途 : |
街路樹、公園樹として植えられる。 蕾は止血・消炎、高血圧の薬用に、また黄色の染料に使われる。樹皮は茶色の染料に。材は床柱や床框などの建築材や、家具・工芸品に使われる。 |
|||
| 備 考 : | エンジュの分類を Styphnolobium 属 とする見解がある。 | |||