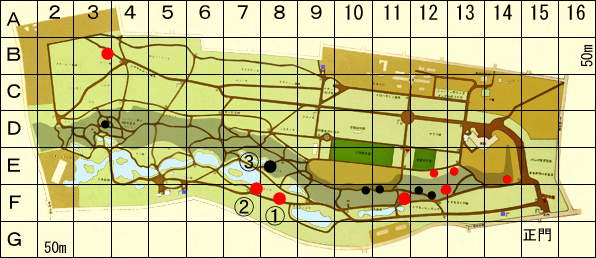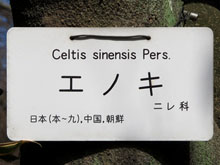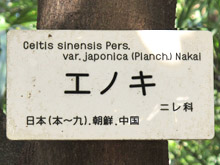| 名前の由来 エノキ Celtis sinensis |
和名 エノキ |
エノキの名前の由来はたくさんあり、どれが定説とはなっていない。
やはり ②番であろうか。
① 枝の木: よく分枝し 枝が多いところから
② 柄の木: 材がやや硬く裂けにくいために器具の柄に使われた
③ 餌の木: 小鳥が好んで実を食べるため
④ 燃えの木: よく燃えるため
⑤ 選りの木: 一里塚に植えられる選ばれた木 エリノキ→エノキ
⑥ サエの木: 道祖神を「サエの神」と呼ぶところから
サエノキ→エノキ
|
|
| 和名 榎 |
一里塚や道祖神の脇に植えられて 一休みする木陰を作るところから、漢字とは別に「夏の木」という意味で使われたようだ。
|
|
| 種小名 sinensis : 中国の という意味 |
|
|
| 英語名 Chinese hackberry |
hackberry はエノキ属一般を指す。
hack は「斧、つるはし」 などの道具のことであり、和名の ②番と同じ。
|
|
| 中国名 朴 樹 pu shu |
由来は不明。 朴 (ぼく) には「木の皮」、「すなお。うわべを飾らない」という意味がある。 エノキの樹皮に特別な特徴はないと思うので、「飾り気のない、変哲のない木」ということだろうか。
|
|
| Celtis 属 : |
紀元前のギリシア詩人 ホメーロス が架空の甘い果実あるいはその木に付けた名前が、後に転用されたものだという。
|
|
| アサ科 Cannabaceae : |
広義のアサは、繊維が取れるほかの植物(アマなど)も含まれる。
由来としては、
① 青い皮から繊維(ソ)を採るところから、「アオソ」が転訛した
② 青割「アオサキ」の略語
③ 「浅い」の意味から などの諸説がある。 |
|
アサ (中国で撮影) |
日本では所持することも
禁止である。
|
 |
|
|
| 旧科名 ニレ科 Ulmaceae : |
15属 200種があり、日本のニレ属 Ulmus には ハルニレ・アキニレ・オヒョウ がある。
植物園には 分類標本園に「アキニレ」があった。
名前の由来は 後日に。 |
|