|
||||
 |
科 名 : | トウダイグサ科 Euphorbiaceae | ||
| 属 名 : | シラキ属 Neoshirakia Esser (1998) | |||
| 旧属名 : | シラキ属 Sapium Jacq. (1763) | |||
| 中国名 : | 白木烏桕 bai mu wu jiu | |||
| 原産地 : | 山形・岩手県以南の山地 朝鮮半島、中国 |
|||
| 用 途 : | 白い材を細工物に、また薪炭材に使われる。以前は 種子から採れる油(シラキ油)を、灯油・塗料・頭髪油として利用した。 | |||
| 小石川植物園の名札は Sapium 属であるが、『植物分類表/大場秀章』、 「GRIN」ともに、Neoshirakia属という 15年ほど前に立てられた新しい属に分類している。 |
| 紅葉するシラキ 2011.11.15. |
 |
| 斜面に生えているため、夏の写真だと周囲の緑に重なってわからないため、まず紅葉の写真を掲げた。トウダイグサ科のシラキは、以前はナンキンハゼと共に Sapium属に分類されていた。花や実の形が似ており きれいに紅葉するなど、ナンキンハゼと共通点が多い。 |
| シラキ の位置 | ||
 |
60番通り |
|
| 仮称 シラキ坂。直接上の段にはつながっていない。 |

| こんな場所に植えるわけはないので、実生だろう。人通りがほとんどない道なので、踏みつけられずに生き残ったものだ。 |
| シラキの幹 | |
 |
 |
| 日が当たると銀白色に見えるが、実際は灰色。近くにあるクロキよりは明るい色である。胸高の直径は 約11センチ。 |
| クロキの幹 |
 |
| 展開した新葉 2011.4.29. | ナンキンハゼ |
 |
 |
| 柔らかい葉で 形はナンキンハゼとは違う。 |
| 花 序 2012.5.5. |
 |
| 新しく出た枝の先に付く。 |
| 成 葉 2012.5.23. |
 |
| 葉の色が濃くなっている。 |
| 雌雄同株 2011.5.24. | ナンキンハゼ |
 |
 ナンキンハゼも 同じ |
| 花序の基部に 数個の雌花が付き、雌花が先に熟す。 |
| 雌性先熟 2012.5.18. | ナンキンハゼ |
 |
 共に花弁は無く柱頭は3裂 雄花は全く開いていない |
| カミキリムシの一種? 2012.5.23. |
 |
| 雄花はまだ花粉を出していないようだが・・・・。 |
| 雄花の開花 2013.5.28. | ナンキンハゼ |
 |
 ナンキンハゼには たくさんのハチが来る |
| 雄花が咲く頃には雌しべの柱頭は枯れていて、すでに子房が膨らんでいる。雌雄の花に時間差があるのは、自家受粉を避けるため と言われている。しかし両者とも、植物園には1本しかないし、近所に植わっている樹種ではない。 |
| 薄手の葉 2002.6.1. |
 |
| 幼果がたくさん生っている。 |
| シラキの若い果実 2013.6.18. | |
 |
 |
| 果実には3裂した柱頭が残っている。子房は3室で 各室に1つの種子。雄花の枯れた花序も まだ付いている。 しかし この後の観察を忘れ、熟した状態は見逃してしまった。 |
| まずは黄葉 2010.11.13. |
 |
| 美しい紅葉 2011.11.16. |
 |
 |
| シラキの 位 置 |
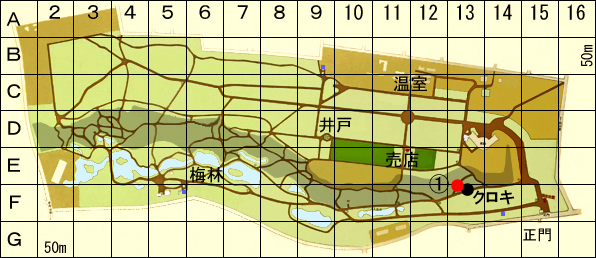 |
| F13 a | ● | 60番通り メタセコイア林の横から右に登る坂の途中 この坂を「シラキ坂」とする |
| 名前の由来 シラキ Neoshirakia japonica | |
シラキ 白木 :材が白いため |
|
|
| 種小名 japonica : 日本原産の | |
|
| シラキ属ほど 何度も属名が変更された例は 珍しい | |||||
| 西暦 | 属名・学名 | 命名者 | 備考・命名の由来 | ||
| 1756 | Sapium | パトリック・ブラウン | 粘る の意味から。属名だけで 種は記載していない | ||
| 1759 | Excoecaria | ジーン・ミューラー | めくらにする、枝を燃やした時の煙で目を痛めるため | ||
| 1767 | Stillingia | リンネ | 英国の植物学者 B.Stillingfleet氏(1702-1771)を顕彰 | ||
| 1790 | Triadica | ローレイロ | 三数性の構造による | ||
| 1846 | Stillingia japonica |
|
|
||
| 1858 | Triadica japonica | バイロン | |||
| 1863 | Excoecaria japonica | ミューラー | |||
| 1912 | Sapium japonicum | パックス、ホフマン | 近年は この学名が使われていた | ||
| 1954 |
Shirakia Shirakia japonica |
古沢潔夫 | シラキ に由来 それまでの Sapium 属との相違点などは不明 |
||
| 1998 |
Neoshirakia Neoshirakia japonica |
Bingtao Li & Hans-Joachim Esser |
新しい シラキ属 の意 中国の研究者による命名 |
||
| Neoshirakia シラキ属 : 新しいシラキ属 | |
|
|
| カナダ ブリティシュ・コロンビア大学のホームページより |
|
| Sapium サピウム属 : 粘る の意味から | |
|
| Triadica ナンキンハゼ属 : | |
|
| トウダイグサ科 灯台草科 Euphorbiaceae : | ||
|
||
|
| 植物の分類 : | APG II 分類による シラキ の位置 |
| 以前、植物の外観や構造などの形態学的な解析で分類していた時には、よくわからない植物が トウダイグサ科に入れられていたという。葉緑素の核酸の塩基配列などを分析する手法の研究が進み、APG
II 分類では、トウダイグサ目は キントラノオ目にまとめられた。 APG分類では、科 や 属 もまとめられることが多いが、トウダイグサ科の中から新たにコミカンソウ科が分けられたり、トウダイグサ科の中で新たな属が作られるなど、研究が進んだ。 |
| 原始的な植物 |
| ↑ | 緑藻 : | アオサ、アオミドロ、ミカヅキモ、など | |||||
| シダ植物 : | 維管束があり 胞子で増える植物 | ||||||
| 小葉植物 : | ヒカゲノカズラ、イワヒバ、ミズニラ、など | ||||||
| 大葉植物 (シダ類): | マツバラン、トクサ、リュウビンタイ、ヘゴ、オシダなど | ||||||
| 種子植物 : | 維管束があり 種子で増える植物 | ||||||
| 裸子植物 : | 種子が露出している | ||||||
| ソテツ 類 : | ソテツ、ザミア、など | ||||||
| イチョウ類 : | イチョウ | ||||||
| マツ 類 : | マツ、ナンヨウスギ、マキ、コウヤマキ、ヒノキ、など | ||||||
| 被子植物 : | 種子が真皮に蔽われている | ||||||
| 被子植物基底群 : | アンボレラ、スイレン、など | ||||||
| モクレン亜綱 : | コショウ、モクレン、クスノキ、センリョウ、マツモ、など | ||||||
| 単子葉 類 : | ショウブ、サトイモ、ユリ、ヤシ、イネ、ショウガ、など | ||||||
| 真生双子葉類 : | キンポウゲ、アワブキ、ヤマモガシ、ヤマグルマ、など | ||||||
| 中核真生双子葉類: | ビワモドキ、ナデシコ、ビャクダン、ユキノシタ、など | ||||||
| バラ目 群 : | |||||||
| バラ亜綱 : | ブドウ、フウロソウ、フトモモ、など | ||||||
| 以前の分類場所 | トウダイグサ目 | ←消滅。ツゲ科、シムモンドシア科、トウダイグサ科 | |||||
| トウダイグサ科 | コミカンソウ属、トウダイグサ属、アブラギリ属、など | ||||||
| マメ 群 : | ニシキギ、カタバミ、マメ、バラ、ウリ、ブナ、など | ||||||
| キントラノオ目 | ヤナギ科、スミレ科、トケイソウ科、トウダイグサ科など | ||||||
| トウダイグサ科 | トウダイグサ属、トウゴマ属、シラキ属、など | ||||||
| アオイ群 : | アブラナ、アオイ、ムクロジ、など | ||||||
| キク目 群 : | |||||||
| キク亜綱 : | ミズキ、ツツジ、など | ||||||
| シソ 群 : | ガリア、リンドウ、ナス、シソ、など | ||||||
| ↓ | キキョウ群 : | モチノキ、セリ、マツムシソウ、キク、など | |||||
| 後から分化した植物 (進化した植物 ) | ||
|
| 小石川植物園の樹木 -植物名の由来- 高橋俊一 五十音順索引へ |
