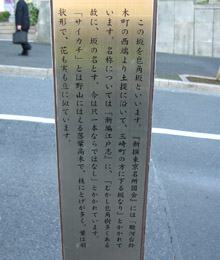サイカチは、枝や 特に幹に、長さ 10cmにもなる鋭いトゲを出す。
これは枝が変化したものだそうだが、とにかく凄まじい。
目でも刺そうものなら、失明してしまう。
このため、多数の果実が生って落下する事と併せて、街路樹には適さない。
|
| 樹形 |

|
|
| トゲの様子 |
 |

|
出たばかりのトゲは、青い色をしている。
時が経つにつれて、濃い茶色→焦げ茶色→黒に近い茶色 と変化していき、古くなると白っぽく枯れた状態となるが、最後までその鋭さは変わらない。
幹からだけでなく、細い枝にもトゲが付く。
葉の付け根 (葉腋 (ヨウエキ) )から刺が出ている事によって、このトゲが 「枝が変化したもの」という説明に納得ができる。 |

|
| 単純な偶数羽状複葉 |
複葉 + 2回複葉 |
 |
 |
短い枝(短枝)に付く葉は「偶数羽状複葉」である。
小葉は少しだけ湾曲したものもあり、きれいな緑色の葉である。
ところが注意してみると、長く伸びた枝の先などには、複葉と2回羽状複葉が組み合わされたもの(右の写真)や、通常の2回羽状複葉がある。
前掲の写真でも、枝に近い3枚は、小葉が6枚と少ないが2回複葉になっている。
自然の不思議、と言えよう。
|
| つぼみ (雄花?) |
花 (雌花?) |
 |
 |
事典によると、花は雌花、雄花、または両生花が付く「雌雄同株」ということである。
さらに、『樹に咲く花』の著者 茂木 透さんの観察によると、同じ木でも、雄花のみが咲く年、雌花のみが咲く年、両方とも咲く年があるそうだ。
これもまた、驚きである。
|
| 若い実 |
12月初めの実 |
 |

|
| 熟した実のアップ |
種子 |
 |
 |
莢の長さは 15~30cmで、軽くねじれるか螺旋状になる。
若い実の写真は、小石川植物園の地面に近いところに生っていたもので、日当たりが悪いために極めて実の入りが悪く、20cmの莢に、小さなタネが3・4個というありさまであった。
日当たりのいい所で育ったものは、同じサイズに15個もはいっている。
種子の大きさは、長さ8~9mm。(切手のサイズは21×25)
|
|
|
サイカチのサヤには、サポニンという泡立つ成分が含まれている。
戦時中、石鹸の配給がストップした時には、ムクロジ、エゴノキとともに、サイカチも石鹸の代用として使われたそうだ。
試しに実をちぎって水に漬け、泡立ててみた。
かなり熟した莢であったため、泡立ちは今ひとつであったが、もっと若いものならどうなのであろうか? |
| なんとか泡立った サイカチ |

|
|
| 名前の由来 サイカチ Gleditsia japonica |
和名: サイカチ : 昔の名前「サイカイシ」がなまったもの |
漢方で種子を「皂角子 (ソウカクシ) 」といい、そこから生まれた 「西海子 (サイカイシ)」という名前が古名として使われていた。
それがさらに転訛したのが「サイカチ」ということである。
莢 (サヤ) も薬として使われるが、こちらの漢方名は「皂莢 (ソウキョウ) 」である。
和名サイカチに「皂莢」の漢字を当てているが、本来、この漢名「皂莢」は、中国原産の別種、Gleditsia sinensis のことで、その現在の中国名:皁莢 の意味は「黒いサヤ」である。
|
|
| 種小名 japonica : 日本の という意味 |
サイカチの原産地は、日本・朝鮮・中国にまたがっている。
本種の命名は 1867年であるが、同じ仲間で中国原産の別種 Gleditsia sinensis が、約80年前の1786年に定義されていた。
このため、G. sinensis に対してサイカチを G. japonica としたのであろう。 |
|
| 命名者は、18世紀のリンネとは ほぼ1世紀違う、19世紀 オランダの植物学者 ミクエル (1811-1871) である。 |
 |
ミクエルの肖像画
Wikipedia より
|
|
| Gleditsia または Gleditschia サイカチ属 : 人名にちなむ |
こちらはリンネと同世代、ドイツの植物学者 グレディチ (1714-1786) を顕彰して名付けられた。
リンネが『植物の属 第2版』に記載したもので、『園芸植物大事典』 でも 『植物の世界/朝日百科』 でも、Gleditsiaの属名が使われている。
ところが 『Index kiwensis』や『原色牧野植物大図鑑』では、属名の綴りが少し異なり、Gleditschia となっている。
植物学者グレディチ のスペルを見ると、なるほど Johann G. Gleditsch である。
すべてのデータを網羅している Index kiwensis には、ちゃんと両方とも記載されており、 Gleditsia も同じ『植物の属 第2版』に記載されていることになっている。
そして その備考には、「Gleditschia と同じ」、となっていた。
リンネがなぜ同じ本に2つの属名を重複して定義したのか。
もしかすると、2つの植物(標本)が、似てはいるが別のもの、と判断して正式に併記したのかもしれない。
順番はどうだったのか、などについては不明であるが、アルファベット順なら、Gleditschia が先である。 |
|
| ジャケツイバラ科 Caesalpiniaceae : |
属名 カエサルピニアは、ローマ法王クレメンス8世(在位1592 - 1605) の侍医で植物学者の、チェザルピーノ(A. Cesalpino ラテン語の綴り Caesalpinus) を記念している。
ジャケツイバラについては 別項を参照していただきたい。
|
|
| トピックス |
さいかち坂 と 漢字名
総武線 水道橋駅から、線路の南側をお茶の水の方に登る坂を「さいかち坂」という。
説明板によると、むかし この坂の脇にサイカチの木が生えていたために名付けられた、ということである。
サイカチの木は一度はすべて無くなったようだが、坂の名前にちなんで、歩道脇のスペースに後から3本が植えられたようだ。
|
| さいかち坂 |
 |
坂の途中から撮った写真で、左側が線路。
左奥の緑が サイカチの木である。
4月末の撮影のため、右側の街路樹 アカバナトチノキ が咲いている。 |
|
トップの「トゲ」の写真は元の3本のものではなく、木から落ちたタネからの実生苗が大きくなった木のトゲである。
線路際の斜面に生えているために枝を切られることがなく、横に長く伸びた優雅な枝振りとなっている。 |

|
さて、
この坂にも名前を示す標識が立てられており、千代田区教育委員会によるその立て札は、「皀角坂」となっている。
|
| 「皀角坂」の標識 |
大分市 ジャングル公園の名札 |
 |

|
|
|
植物名としての「サイカチ」や「漢方の名前」の表記に、事典などによって数種の漢字が使われているので 調べてみた。
|
まず坂の標識であるが、2006年にプレートを張り直した気配がある。
そして『新編江戸志』という文献に、 「むかし皀角樹多くある故に、坂の名とす。」とかかれていることを引用している。
引用する時に、ミスをすることはないであろう。
だからこそ、堂々と「皀角坂」と明記しているわけである。 |
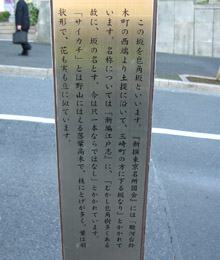 |
『樹と花の大事典』の見出し、漢方名も「皀」の字を使っている。
|
 |
ところが、通常使われているのが「皂莢」の字である。
これが正解だと思われるが、朝日百科『植物の世界』には、「漢名としての皂莢は、本来 Gledistia sinensis を指す。」という注意書きがある。
あくまで「本来」であって、皂莢が間違いだと言っているのではない。
各国の一般名称 (common name) やその表記方法については、「内政干渉」する必要はなく、日本では「サイカチ」を皂莢とし、中国では「シナサイカチ(仮名)」が皂莢でも問題は ない。
その「シナサイカチ」の中国名だが、『園芸植物大事典』では「皁莢」となっている。
以下は『字通』/白川 静 および 『日本国語大事典』/小学館 で調べた結果である。
|
| 文字 |
読み |
意味・解説 |
| 皀 |
ヒョウ
キュウ
キョウ |
かんばしい。 穀物の良い香り。
「白」の部分は例えて言えば、米がモミの中に在る形を表す。 「ヒ」の部分は匙で扱うことを示す。 |
| 皂 |
ソウ |
皁 の俗字 『日本国語大事典』(出典:正字通) |
| 皁 |
ソウ
ゾウ |
しもべ、馬屋、かいおけ、黒い、黒い布、早い、
橡などの実、しいな
|
|
となると、正しくは現在の中国名「皁莢」ということになる。
また、皂莢 の意味が、黒いサヤだということがわかる。
|
|
|
余談であるが、坂の途中に「皂莢坂ビル」という名の建物がある。
こちらは 正しい字を使っているが、屋上のビル名は「さいかち坂ビル」と平仮名である。
漢字では読み方がわからないためであろう。
|
| 皂莢坂ビル |

玄関脇の植え込みに、サイカチの木が1本だけ植えられ、20cm強になっていた。
もちろん幹からは刺が出ている。 |


|
そして、読み人知らずの小さな句碑があった。
皂角子の 実はそのままの 落葉哉
|
| サイカチを読んだ句碑 |

こちらも「皂」の字が使われている。
|
|
|
参考文献 : Index Kewensis Ver.2.0/Oxford University Press、
園芸植物大事典/小学館
週間朝日百科/植物の世界・朝日新聞社、
植物学名辞典/牧野富太郎・清水藤太郎、
樹と花の大事典/植物文化研究会
漢和中辞典/角川書店、
字通/白川 静、
日本国語大事典/小学館 |
|
| 世界の植物 -植物名の由来- 高橋俊一 五十音順索引へ |